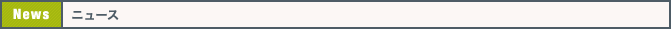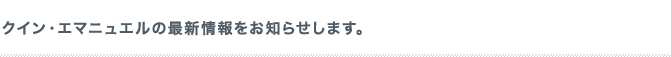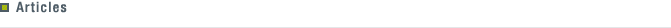お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
スポリエーション(証拠隠滅)に注意 (11/06/28)
「スポリエーション(証拠隠滅)」は、弁護士以外のほとんどのアメリカ人がおそらく知らない英単語である。スポリエーションは、証拠の破壊若しくは重大な変更又は係属中又は合理的に予想される訴訟において他者に証拠として利用されるものを保存しないことをいう。スポリエーションは、米国の訴訟に関与する会社が、文書又は証拠を保存し又は提出する法的義務を怠ったときに問題となる。
米国の訴訟に関与し又は関与する可能性がある日本企業が、関係のある記録や文書のような証拠となる可能性があるものを保存する法的義務について理解しておくこと、及び、スポリエーションの主張のリスクについて理解しておくことは決定的に重要である。より大量の文書やデータが電子的に保存されるようになるにつれて、この義務に従うことはより複雑なものになり、リスクはより大きなものになる。会社がスポリエーションを行った場合、深刻な結果が招かれる。例えば、訴訟の完全な終了、スポリエーションを行った当事者に不利な陪審説示、違反当事者に特定の主張や特定の証拠の提出を認めない決定、又は、報酬及び費用の支払である。証拠となる可能性があるものの保存義務があると現実に知らなかったこと(つまり、無知)は、スポリエーションの有効な抗弁とはならない。米国の裁判所は、同様の事実関係にある合理的な当事者であれば訴訟を合理的に予想し、それゆえ証拠を保存する義務を負うかという客観的な基準を用いる。
スポリエーション及び証拠となる可能性があるものの保存義務についてより理解するため、日本企業には、2011年5月13日に出された二つの裁判所の判断について検討してほしい。Micron Technology v. Rambus, 2009-1263(以下「Micron事件」という。)及びHynix Semiconductor v Rambus, 2009-1299(以下「Hynix事件」という。」)において、連邦巡回区控訴裁判所は、特許侵害訴訟における証拠の破壊の問題について直接審理し、判断を行った。
Micron事件及びHynix事件
Rambus, Inc.(以下「Rambus社」という。)の主要な事業は、同社の特許の実施許諾を行うことである。
Rambus社は、実施料率を設定し、また、裁判所から同社の特許が有効であるという判断を受けるために、1998年12月までの間に、訴訟戦略を立案し、訴訟が必要であると判断し、訴訟の相手方を特定し、クレーム・チャートを作成した。1999年8月26日、Rambus社は、「シュレッダー・デー」を行い、300箱の文書を破棄した。Rambus社は、破棄されたものについて記録を有しておらず、同社の従業員に対しては、予想される訴訟に役立つ文書を保存するように指示を行った。1999年9月24日、Rambus社の取締役会において、訴訟を提起すべきという提案が行われた。1999年10月22日、Rambus社は、日立に警告書を送付し、2000年1月18日、日立に対して訴訟を提起した。
これらの事実の下で、デラウエア州地方裁判所は、Rambus社は1998年12月までには文書の保存義務を負っていたと認定し、また、Rambus社は1999年8月に300箱の文書をシュレッダーにかけたときにスポリエーションを行ったと認定した。デラウェア州地方裁判所は、Rambus社がスポリエーションを行ったことを理由に、Rambus社の12の特許は強制力がないと判示した。
他方、カリフォルニア州北部地方裁判所は、Rambus社の証拠保存義務は1999年9月まで存在せず、そのため、同社が1999年8月に文書を破棄したことはスポリエーションとはならないと認定した。カリフォルニア州北部地方裁判所は、Hynix事件においてトライアルを行い、これによってHynixに3億9700万ドルの支払を命じる判決が出された。連邦巡回区控訴裁判所は、二つの地方裁判所の間での判断の齟齬を調整しなければならなかった。
連邦巡回区控訴裁判所は、Rambus社が1999年8月にスポリエーションを行ったというデラウェア州地方裁判所の認定を支持したが、Rambus社の特許に強制力を認めないとする制裁は取り消した。Micron事件は、制裁について決定するために差し戻され、デラウェア州地方裁判所は、Rambus社が不誠実(bad faith)であったか否かについて審理するように命じられた。Hynix事件では、Hynix社に3億9700万ドルの支払を命じる判決は取り消され、カリフォルニア州北部地方裁判所は、Micron事件の判決を考慮し、スポリエーションに関する判示について再検討することを命じれられた。
文書の保存義務が発生する時期について、連邦巡回区控訴裁判所は、「文書を保存する義務が生じる時期を決定するための適切な基準は、合理的に予想される訴訟という柔軟な基準であり、この基準には追加の注釈を必要としない。」と述べ、柔軟な基準が適用されるべきであると論じた。最近のMicron事件及びHynix事件の判決は、より明確な基準を提示していないとして批判されてきたが、これらの事件は、特に特許権侵害訴訟及び文書保存方針に関し、日本企業がスポリエーションの問題にどのように対処すべきかということについて、いくらかの指針及び明確さを与えている。
日本企業への教訓
証拠のディスカバリーは、訴訟手続きの一部として、アメリカの当事者対立主義のシステムの根幹となっている。ディスカバリーシステムは、いかに慎重な取り扱いを要するものであっても、秘匿特権によって保護されず、争点に関連する可能性のある証拠については、各当事者がその全てを他の当事者に提出しなればならないという思想に基づいている。 このシステムが正常に機能するためには、各当事者が他の当事者から証拠を獲得する機会を平等に有していなければならない。連邦控訴裁判所は、訴訟が係属しているか、または、合理的に予見可能であるときには、書類保存義務は2つの競合する利益のバランスをとるようにするべきものであると理解している。一つは、訴訟がアメリカで行われる可能性が否定できない場合に特に問題となるものとして、完全開示主義と証拠の破壊防止の要請である。もう一つは、企業に既にビジネスの役に立たない記録を廃棄することを許容する、不必要な書類とデータを廃棄するビジネス上の正当な利益である。連邦控訴裁判所は、企業がしばしばこれらの二つの利益のバランスをとった書類保存方針を採用しなければならないことを知らしめている。
Micron事件とHynix事件から得られる日本企業への教訓は、書類保存に関する企業内部の方針は重要であり、必要であるということである。企業の書類や電磁的記録が長期にわたって採用されている方針に従って定期的に廃棄されているということであれば、スポリエーションの主張の防止やそれに対する防御はより容易であろう。適切に整備された書類保存方針は、書類等の廃棄が「善良な維持管理」目的によって、ビジネス上の必要性によりなされたものであるとの事実を支えるものとなる。企業は、いついかなる書類が不必要になって廃棄されるかを出来る限り明確に規定するべきである。また、どの書類が貴重なもので保存されるべきものかも明確にすべきである。適切かつ適正に施行された書類保存方針は、書類の廃棄が企業の訴訟戦略を推進するためのものではなく、また、相手方当事者の事実発見を阻害する目的でなされたものでもないことの証拠となりうる。
日本企業の書類保存方針は、潜在的な訴訟との関係でとられるべき手続きを説明するものでもあるべきである。日本企業が「合理的に予見可能な」訴訟に直面したとき、関連する証拠の保持とその破壊の防止のための企業内部の規則や手続きが存在している必要がある。例えば、「訴訟用保存通知」(Litigation Hold Notice)を準備する必要があるし、また、訴訟に関連する記録や証拠を保持している部署や個人に対し通知を配布する責任者を決めておく必要がある。また、定期的に予定されている書類の廃棄は停止する必要がある。スポリエーションが厳しい結果を伴うものであることからすれば、書類保存方針を整備・施行するために、知識豊富な米国の弁護士から法的な助言を受けることはよい考えである。
備考:クイン・エマニュエル・アークハート・サリバンは、デラウェア州連邦地方裁判所でMicron事件のトライアルを取り扱っていました。クイン・エマニュエル東京オフィスは喜んで、スポリエーション問題の詳細な説明のためお会いしますし、日本企業の記録保存方針の作成や実践のお手伝いをさせていただきます。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所
ウェイン・アレキサンダー
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com