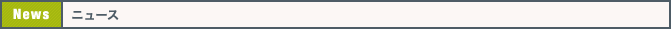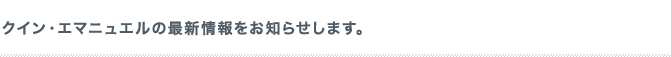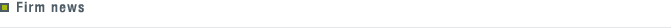お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
米国改正特許法について、レポート記事をアップしました。 (12/10/29)
米国改正特許法 審査手続きがよりトライアルに近いモデルへと明確にシフト
2011年6月にオバマ大統領が署名したリーヒ・スミス米国発明法(以下「新法」)は、アメリカ特許法において、過去100年を超えるスパンで見ても、最も大きな変化をもたらすものである、新法により、すでに確立されたアメリカ特許法は大小さまざまに改正されることになる。また新法によって、頻繁に特許侵害訴訟のターゲットになっているが、連邦裁判所の長期に亘る訴訟は避けたいと考えている企業のため、現在利用可能な特許庁での登録後審査手続が拡張される。
今回の改正は、様々な側面に及んでいる。新法の規定によって、連邦上の訴訟も重大な影響を受ける。侵害訴訟における被告の「最良実施態様」の抗弁は禁じられ、また、特許権者が一つの侵害訴訟で多数の被告を訴えることを大幅に制限した。
最も根本的な改正―アメリカの特許制度を先発明主義から先願主義へと転換するもの―は、2013年2月16日、法の最終施行に伴い発効する予定である。
本年9月16日に施行された第2次改正では、新しい当事者間審査手続(現行の当事者間再審査手続に代わるもの)及び登録後審査手続が定められている。特許庁で特許の有効性を争い、迅速な手続を求める者にとっては、新しい選択肢が増えることになる。
そして、審査手続きは、よりトライアルに近いモデルへとシフト。本稿では、今秋に施行される二つの手続きの特徴、ならびに留意点について報告する。
新しい当事者間審査手続(当事者系レビュー New Inter Partes Review Procedure)
※現行の当事者系再審Inter Partes reexamination の名称を改めたもの
審査件数の上限が発生。各年初めに新規申し立てが殺到の見通し
長年、当事者間再審査手続は、特許の有効性を争う当事者が好んで利用してきた。しかし、2012年9月16日以降、同手続は廃止される。代わって登場する当事者間審査手続は、今後の訴訟及び訴訟戦略に大きなインパクトを与えるであろう。一例として、膨大な審査申立てに特許庁が忙殺されるのを防ぐメカニズムとして、新法は、この新しい手続の開始以降最初の4年間は、特許庁のディレクターが当事者間審査の年間上限件数をあらかじめ定めておき、これを超えた場合には申立てを制限することができるものと定めている。したがって、もしこの当事者間審査手続が広く利用されるようになると、件数オーバーによる門前払いを避けるため、各年の初めに新規の審査申立てが殺到することが予想される。
新法は、同時に、特許付与後の審査を開始するための要件を厳しくした。従前の当事者間再審査手続では、申立てが特許性に関する新規で本質的な問題を提起することが必要とされていた。新法は、一方的再審査手続又は新しい当事者間審査手続の開始要件として、この基準を変更し、少なくとも一つの特許のクレームについて特許無効又は変更請求の合理的な勝訴可能性を立証することが必要とした。理論上は、このように基準が厳しくなったことにより当事者間審査手続の申立ては制限されることになるが、実際には、統計によれば、この新しい基準によっても特許庁が認める当事者間再審査手続の割合に大きな変化はないとの見方もある。しかし、たとえこの新しい基準によって特許庁において手続開始が認められる割合が減ったとしても、特許庁がクレームの有効性を判断する基準は新法でも変更されていないことから、理論上は、その減少に比例して、特許無効の申立てが成功する割合も増加するということになろう。
当事者間審査手続によって争われる特許の世界は、従来の当事者間再審査手続によるそれより大きいものとなりうる。従来の法の下では、特許を争う者が当事者間再審査手続を申し立てられるのは、1999年11月29日以降に出願された特許に限られていた。新法はこの制限を廃し、すべての特許について当事者間審査手続が利用可能であるものとした。もっとも、当事者間審査手続は、特許登録直後には利用できず、(1)特許登録後9ヵ月後、又は(2)登録後審査(新法によるもう一つの審査手続。後述。)の終了のいずれか遅いときに初めて利用可能となる。
特許庁の審査と連邦裁判所による無効審理が重複することを避けるため、新法は、特許を争う者に対し、新たな制約を課している。まず、すでに特許無効に基づき民事訴訟(宣言的判決を求める訴え等)を提起している者は、当事者間審査手続を利用できない。従前の訴訟(特許権者が提起した侵害訴訟等)で特許無効の抗弁を提出したとしても、当事者間審査手続の申立ては禁止されない。しかし、この場合、侵害訴訟の訴状送達時から1年以内に申し立てなければならない。
手続きの形式がよりトライアルに近いモデルへとシフト
従来の再審査手続の廃止と新しい審査手続の採用によって最も大きな影響を受けるのは、手続の形式である。従来の再審査手続の進行は、基本的に特許審査手続モデルを踏襲していた。すなわち、特許を争う者に主張立証の機会が与えられるほかは、審査官が、通常の審査と同様に再審査を行うというものである。新しい審査手続は、このモデルを廃止し、よりトライアルに近いモデルへと明確にシフトした。新しい手続のために提案されたルールは、未確定の部分も含むが、これらの新しい手続における、限定されたステップによる関連情報のディスカバリー(宣誓書、宣言書を提出した証人のデポジションを含む。)、プロテクティブ・オーダーの利用、ディスカバリーの濫用に対する制裁、当事者による口頭弁論の権利、審査申立てから5ヶ月以内に行われる審査を開始するかどうかの決定、開始決定から1年以内の最終判断(合理的理由あれば6ヶ月の延長可能)等が提案されている。すべての手続は、3人以上からなる合議体(新たに創設される特許審理上訴委員会)によって行われ、その決定については、連邦巡回控訴裁判所に上訴が可能である。委員会の決定を地方裁判所で争うことはできない。
最後に、第三者はいったん開始した手続を終結させることができない現行の再審査手続と異なり、新法では、当事者が共同で特許庁に対し、和解したことを理由として、その審査を終結させるよう申立てを行うことができるようになる。特許庁は、終局的な決定を行っていない場合には、この申立てを認めることができる。特許権者と申立人の合意等は、書面でなされ、かつ審査終結前に特許庁に提出されなければならない。当事者は、さらに、特許庁に対し、この合意等を非公開とし、特許記録に掲載しないよう求めることができる。申立人は、将来のあらゆる民事訴訟やITCの手続において、すでに当事者間審査手続で主張し又は主張し得た事由に基づいてクレームの無効を主張することは一般的にできないが、特許審査の却下に成功した者については、禁反言は適用されない。
新しい登録後審査手続 (New Post Grant Review Produce)
上述したとおり、新法は、新しい登録後審査手続を創設した。この手続に関する規定の施行日は2012年9月16日であるが、この規定は2013年3月16日以降に出願された特許に適用されるため、登録後審査手続が適用されるまでには時間差がある。
新法による登録後審査手続は、2つの重要な違いを除いて、当事者間審査と同様である。違いの1点目は、登録後審査は特許の登録後9ヶ月以内に申し立てなければならないという点である。2点目は、申立て理由が刊行物又は特許に基づく無効主張に限られている当事者間審査と異なり、登録後審査では、あらゆる無効理由を主張することができる(最良実施の非開示を除く。)という点である。たとえば、登録後審査は、発明の先行販売又は販売勧誘を理由として申し立てることができる。
他方、限定的なディスカバリーが行われる点、口頭弁論が可能な点、3人以上からなる特許審理上訴委員会によって行われ、連邦巡回控訴裁判所に上訴が可能である点、開始決定から1年以内の最終判断(合理的理由あれば6ヶ月の延長可能)、和解による終結等は、当事者間審査手続と同様である。
この二つの改正点について、メリット、デメリットをまとめておく。
当事者間審査手続について
特許を争う者にとって、再審査手続(当事者間又は一方的)に比べて有利な点
- デポジション(証言録取)や専門証人のオピニオン取得を含む限定的なディスカバリーが利用可能。
- 手続係属後1年以内に終局判断→再審査手続に比べて格段に速い。
- 審査官ではなく、特許審判上訴委員会(PTAB)による審査。
- 当事者間の合意による手続の終了が可能。
- すべての登録特許について利用可能(従前の当事者間再審査手続は、1999年11月29日以降に申し立てられた特許に対象が限定されていた。)。
不利な点
- 主張し又は主張しえた防御方法は、後の別訴で主張できない(現行の当事者間再審査手続と同様だが、一方的再審査手続とは異なる。)。
- 訴訟寄りの手続になるため、コストが嵩む。
- 施行後最初の4年間は、件数制限あり。
特許を争う者にとって、地方裁判所での訴えに比べて有利な点
- 手続係属後1年以内に終局判断。もし同時に地方裁判所に訴えが継続中の場合、当事者間審査手続終了まで審理が停止する可能性が高い。
- 1年以内に終結するため、コストは地方裁判所よりかなり低く抑えられる。
- 地方裁判所と同様、ディスカバリーが利用可能だが、無効主張に関する争点に限定されているため、コストを節約できる。
- 有効性が推定されない。
- 無効の立証は、明白かつ確信を得るに足る証明ではなく、証拠の優越で足りる。
不利な点
- 主張し又は主張しえた防御方法は、後の別訴で主張できない。
- 無効主張の根拠になし得るのは、印刷された刊行物のみ。
- 施行後最初の4年間は、件数制限あり。
新しい登録後審査手続について
特許を争う者にとって、再審査手続に比べて有利な点
- 最良実施を除き、あらゆる無効理由が主張可能。
- デポジション、専門証人のオピニオンを含む限定的なディスカバリーが利用可能。
- 手続係属後1年以内に終局判断→再審査手続に比べて格段に速い。
- 審査官ではなく、特許審判上訴委員会(PTAB)による審査。
- 当事者間の合意による手続の終了が可能。
不利な点
- 特許登録後9か月以内の申立てが必要
- 2013年3月16日以降に出願された特許についてのみ利用可能。
- 主張し又は主張しえた防御方法は、後の別訴で主張できない(現行の当事者間再審査手続と同様だが、一方的再審査手続とは異なる。)。
- 訴訟寄りの手続になるため、コストが嵩む。
特許を争う者にとって、地方裁判所での訴えに比べて有利な点
- 手続係属後1年以内に終局判断。もし同時に地方裁判所に訴えが継続中の場合、審査手続終了まで審理が停止する可能性が高い。
- 1年以内に終結するため、コストは地方裁判所よりかなり低く抑えられる。
- 地方裁判所と同様、ディスカバリーが利用可能だが、無効主張に関する争点に限定されているため、コストを節約できる。
- 有効性が推定されない。
- 無効の立証は、明白かつ確信を得るに足る証明ではなく、証拠の優越で足りる。
不利な点
- 特許登録後9か月以内の申立てが必要
- 2013年3月16日以降に出願された特許についてのみ利用可能。
- 主張し又は主張しえた防御方法は、後の別訴で主張できない。
特許庁、特許訴訟解決の場へシフト
特許の有効性を争うこれら2つの新しい登録後手続は、同時に、企業に対し、特許侵害の主張にどのように対処するかについて長期的な戦略を再度検討することを迫るものである。もちろん、未だ公表されたに過ぎない段階にある各規定の最終的な内容次第ではあるが、特許に精通した裁判官によるトライアルに似たシステムが利用可能になるため、特許庁が特許争訟の解決の場として活用される機会が増えるであろう。しかし、企業は、特許庁で特許の有効性を争う手続が審査的手続からトライアル的手続に変容することによって、状況が大きく変わり、侵害主張に対する戦略的アプローチも構築しなおす必要があることを認識すべきである。この新しい手続においては、訴訟、証人、トライアルに関するスキルがきわめて重要になり、成功するための戦略アプローチは、特許審査手続ではなくより訴訟実務に近いものになるであろう。