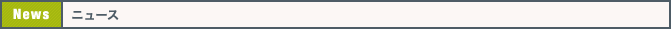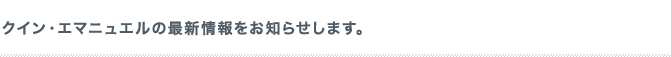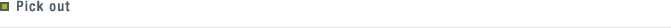お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
AAA商事仲裁規則の重要な変更 (14/02/26)
アメリカ仲裁協会(American Arbitration Association)規則(「本規則」)はアメリカで最も広く利用されている規則である。クインエマニュエル・ロサンゼルスオフィスのパートナーであり、アメリカ仲裁プラクティスの議長でもあるFred G. Bennettは、AAAのタスクフォースの座長を務め、AAAの役員と協同し、近時重要な規則の改正を行った。タスクフォースのプロジェクトは、国内の最も優れた仲裁実務家と仲裁人からの情報提供を基に数年をかけて大掛かりに行われた。この過程を反映して、本規則の改正は、面談者の要望であるより合理的・経済的かつ計画的な手続を目指して行われた。本改正規則は、手続の順調な進行すなわち当事者が経済的かつ迅速な紛争解決のために意味を有する争点に集中することを促すものである。手続への誠実な関与が改正の中心的テーマである。本稿では、特に注目すべき変更点と本改正規則がどのようにそれを利用する当事者に影響しうるかという点について述べる。
参加者の早期の関与
新規則の主目的は、手続全体の迅速化のために、当事者、その弁護士、仲裁廷を仲裁手続の早期の段階で関与させることにある。本改正規則は、仲裁を前進させうる実質的な争点について当事者に仲裁手続の早期の段階で真剣に検討を行わせることで手続を進行させることを意図する多くの原則的ルール及び手続を定めた。これらの改正により、特に仲裁手続の早い段階において当事者が次に何をすべきかについて不明瞭である又は混乱が生じるという「死角」がなくなった。
本規則21条は、仲裁人の選任後、「仲裁の規模及び複雑さに応じ」、仲裁人の裁量により、予備審理が「可能な限り速やかに設けられるべき」であることを認めている。特に、規則は当事者自ら審理に参加することを促している。予備審理の本質的な目的は予定されている手続の基準を定めることであって、本改正規則において想定されている手続は、連邦裁判所で出される審理日程についての命令(scheduling order)とは大きく異なるものである。実際に、予備審理手続規則(Rules’ Preliminary Hearing Procedures)が定める手順(P-1及びP-2)は、仲裁には不適切であろう「裁判所における手続を持ち込むこと」を明示的に警告している。
P-2に列挙されているチェックリストは協議に先立って各当事者が仲裁について戦略と予定を立てておくことを求める事項を広く含んでおり、とりわけ、調停の可能性、書面修正の可能性、適用される手続法及び実体法、決定的争点に決着がつく可能性、審理の分割の可能性、審理手続それ自体、並びに事前審理及び審理の日程が含まれている。P-2はまた、仲裁廷が、審理中になされた決定が記載されている命令書を作成することを義務付けている。
予備審理に加えて、仲裁人の選任前においても効率的な事案の処理ができるように、いくつかの規則が改正・加筆された。本規則11条はその一例である。従前の規則(本規則10条)は、仲裁地は、当事者の合意により又は一方当事者の要求に対して他方当事者が適時に異議を申し出なかった場合に上記要求により決定されるという第一次的な手続を定めていた。本改正規則11条は、この「黙示の同意」を削除することで仲裁地決定の問題を明確にし、当事者が合意できない場合には(明示のガイドラインに従い)AAAに適切な仲裁地を決定する権限を付与するものである。AAAのこの過程への関与は、公正な結果をもたらすことに加え、入口段階における争いにより仲裁が引き延ばされることを避けることが意図されている。
本規則12条は、AAAが作成した登録者名簿から仲裁人を選任する手続を修正するものである。規則は、リストに掲載されている中立者に対する当事者の異議を一切放棄させることとし、双方当事者が各自のリストを交換する必要はないこと、リストを返還しない場合には返答を怠った当事者のみが影響を受けることを明確にしている。本規則43条は、当事者及び仲裁廷の事前の許可を得る必要なく、当事者に電子メールによって通知を送ることができることを認める。これらの改正は、単純かつ比較的小さなものであるが、新しい本規則全般の核となるテーマ、すなわち仲裁を迅速な解決へと前進させることに沿うものである。
より合理的なディスカバリ手続
新しい規則は、仲裁におけるディスカバリの基準を明確にし、関連する情報、特に電子的に保管された情報の完全かつ公正な交換を確実に行うための方法論を明確にする変更を行った。当事者は、裁判手続における広範なディスカバリの出費と負担を避けることを見越して仲裁に合意することも多い。本改正規則は仲裁廷及び当事者の個々の責任に関してより明確なガイドラインを含んでいる。それらは当事者が紛争の実体についてのディスカバリに集中するインセンティヴを与えることと、当事者の協同及び必要な場合には仲裁人の強化されたディスカバリ権限を通じて手続を迅速化させることを目的としている。
本規則22条の下において、仲裁廷は現在、効率的な紛争解決を促進するために予備審理での情報交換についてより大きな力を有している。これらの権限には、各当事者が依拠しようとする資料の交換を要求する権限、当事者に文書の交換を更新するよう命令する権限、当事者に対し、「争点についての結論に関連し、かつ重要」な文書であって当事者が保持又は管理しているもの(その他の方法によっては反対当事者がそれらの資料を容易に入手できないものに限る)を提出するよう要求する権限が含まれる。この「関連し、かつ重要」の基準は、原則的には推奨されるディスカバリの範囲を定めるものであって、連邦裁判所や多くの州裁判所におけるディスカバリの基準である「証拠能力ある証拠に合理的に到達できると予測される」というものよりも狭いことが重要である。それゆえ、当事者には証拠漁りやその他の無駄なディスカバリの努力を行うことに対するインセンティヴが働かないのである。
本規則23条は、ディスカバリ手続に集中するための道具を仲裁廷に与えている。たとえば仲裁廷は、必要に応じて電子データの検索基準を作成し、ディスカバリ費用を分配することができる。これにより仲裁廷は、ディスカバリ期間中に公正かつ迅速な情報交換を確実に行うにあたってより本質に関わる積極的な役割を果たすことができる。本規則23条は、仲裁人が、故意の不遵守に対しては不利な推認を行うことができることや費用についての仮裁定を下すことを含む強制命令を下す権限を明示的に認めている。
本改正規則において念頭に置かれているディスカバリの違いは、改正版の「大規模複雑商事紛争の手続(Procedures for Large, Complex Commercial Disputes)」において強調されている。これは、当事者の合意なき限り50万ドル以上の請求にかかるすべての仲裁に適用される本規則の特則(現在のL-1からL-3)である。旧版のL-3(従前のL-4)の下では、証言録取(deposition)及び質問書(interrogatories)は「当該事項を決定するために必要な」情報を有する者に対して「正当な理由が示された場合」に認められていた。新しいL-3は本規則22条及び23条の「争点についての結論に関連し、かつ重要」の基準を取り入れ、正当な理由が示された「例外的な場合」においてのみ仲裁廷は証言録取を許すものと定めている。さらに、仲裁廷は証言録取に要する費用を分配することができる。これらの改正は、ディスカバリの1つの形式(質問書)を完全に撤廃しつつ他方の形式(証言録取)を「例外的」なものとし、かつ費用の相手方負担が認められうるとすることで、無駄なディスカバリ戦術へのインセンティヴをなくしている。本改正規則は、ディスカバリの過程を当事者が完全に支配することから当事者を保護しようとするものでもある。旧版のL-3の下では当事者は合意したとおりのディスカバリを行うことができたが、新版の下においては当事者は本規則22条に従ってディスカバリを「行わなければならない」のである。
準義務的調停
本規則は現在、本規則9条により、請求又は反訴請求が75,000ドルを超える紛争について、当事者は調停を行う「ものとする」とし、義務としている。いずれの当事者も、AAA及びその他の当事者に通知することにより、ここから離脱することができる。しかし、新規則は、調停を回避するために積極的な行動を必要とすることにより、基本的にすべてのAAA仲裁に調停手続を組み込んでいる。規則は、調停手続に大きな柔軟性を持たせている。すなわち、調停が「仲裁手続を遅延させるものでない」限り、仲裁中のいかなる時点においても、調停を行うことができる。この運営上の事項は些細なことに見えるが、より重要な実務上の意味を持っている。すなわち、本案前の調停とは異なり、同時並行で行われる調停は、当事者が手続を長引かせて紛争解決を遅らせるために調停を悪用することを防止する。
非協力的な当事者を罰する手段の追加
本規則9条に基づく義務的な調停は、より協力的な雰囲気を穏やかに醸成しようとするものであるが、本改正規則のその他の部分は、非協力的当事者の問題に対処する上でより強力な姿勢を取っている。本規則の改正前は、命令を強制し、非協力的な当事者に対処するための仲裁廷の権限は暗黙のものであり、規則中に包括的に明記されたものではなかった。その結果、仲裁人の権限が実際にはどこまでに渡るのかが不明確となることがあり、仲裁人は、仲裁手続の終わりに費用や報酬の分担を決める以上のことは控える傾向にあった。本改正規則は、現在、仲裁廷が用いることができる包括的な一連の強制手段について定めている。
当事者が本規則に定める義務又は仲裁廷が出した命令に違反した場合には、仲裁廷は、本規則新58条に基づいて、当事者の要求により、違反当事者に制裁を課すことができる。もっとも、制裁が実質的な仲裁手続に及ぼす潜在的な影響に対する懸念から、本規則58条は、制裁の要求を受けた当事者に対し、一連の手続面での保護を与えている。当事者は、仲裁廷が制裁を決定する前に、当該要求に反論する機会を与えられなければならない。「当事者の仲裁への参加を制限し、又は争点についての不利な決定をもたらす」あらゆる制裁命令は、双方当事者による証拠の提出と法的議論を経た後で出されなければならないとされている点は、重要である。また、いかなる制裁命令も仲裁廷が書面で説明しなければならず、これにより、仲裁の経過に著しく影響を及ぼしうるあらゆる制裁の記録が作成される。最後に、本規則58条は、仲裁廷が制裁として欠席仲裁判断(default award)を出すことを明確に禁止する。
同時に、本規則57条は、仲裁を回避しようとする当事者が一般的に用いる方策(発生した仲裁費用の支払の全面拒否)を防止する。これは、例えば、相手方が反訴を請求して、当事者双方とも運営費用の支払を請求される場合に起こる可能性がある。新旧いずれの本規則57条においても、いかなる当事者も、仲裁手続を継続させることができるように、他方当事者が負う未払いの費用を前払いすることができる。しかし、改正規則の下では、当事者は、仲裁廷に「当事者の不払いに関して特別な手段を取る」こと(「自らの請求を主張し追及する当事者の能力を制限すること」を明確に含む。)を求めることができる。本規則58条と同様に、本規則57条は、現在、「制裁を課される」当事者に対する保護を規定している。すなわち、本規則57条に基づく救済の要求を受けた当事者は、反論の機会を与えられなければならない。仲裁廷が「当事者の仲裁への参加を制限する」命令を出すには、「適切な支払を行った」当事者が、仲裁廷が必要とする証拠を提出しなければならない。
公正な証拠審理を確保するための柔軟性の追加
改正後の本規則35条(本規則旧32条)は、より効率的な仲裁手続を促進し、証拠の提出における柔軟性をより高めるために改正されている。条文の文言が、本規則旧32条の「宣誓供述書(affidavit)」から本規則35条の「書面による陳述(written statement)」へと変更されたことが示すとおり、本規則35条は、一般的な実務として増加しつつある仲裁手続における書面による証人の陳述(written witness statement)の利用を強調している。関連するすべての証拠が審理において完全に提出されることを確保する助けとするべく、本規則35条は明確に、「電磁的又はその他の方法」による審理(例:電話又はビデオによる審理)の利用を認め、また、「本質的な」証言をする証人が、仲裁廷の面前で証言を行うべく召還されうる場所に、一時的に審理の場を移すことも認める。そして、当事者が証人を利用可能とすることを促すため、また、命令に従わせる追加的な手段を仲裁廷に与えるために、仲裁廷の要請後、証人が尋問に出頭しなかった場合には、仲裁廷は、その証人の陳述や報告を無視する権限を明示的に与えられている。
仲裁パネル選任前の緊急の救済
本規則に行われた数多くの改正は、当事者に緊急救済(emergency relief)の選択肢を提供している。これらの改定は、本規則の簡易手続(Rules’ Expedited Procedures)(E-6)に基づく書面のみによる手続の上限を10,000ドルから25,000ドルに増額するような微調整から、緊急救済獲得のための手続を本規則の本体(本規則38条)に正式に組み込むような大きな追加まで、幅がある。
AAAの本規則は、現在は本規則38条にその実質的な部分が具現化されている緊急救済を、緊急措置の随意規則(Optional Rules of Emergency Measures)及びAAAの国際規則(AAA’s International Rules)において認めた。本規則新38条は、緊急救済を、商事仲裁規則(Commercial Arbitration Rules)の本体中に完全に成文化している。これは、実務的には、新たな本規則の効力発生日より後に締結されたあらゆる仲裁条項は、その条項が明示的に関連規則を組み込む必要なく当然に、緊急救済を含むことを意味する。
緊急救済と暫定的措置(interim measure)との区別には、注意を払うべきである。本規則37条は、仲裁廷に、差止め及びその他仲裁廷が「必要と判断する」救済措置を認める権限を付与しており、これは旧規則にも存在した。これに対し、本規則38条は、仲裁廷が選任される間の一時的な救済の申立てを検討し、認める緊急仲裁人(emergency arbitrator)の簡易な選任手続について規定する。本規則38条に基づき、当事者による緊急救済の申立てから1営業日以内に、1人の緊急仲裁人が選任される。申立当事者は、求める救済が認められるべき理由及びその救済が緊急に必要である理由の双方を説明しなければならない。
本規則38条は、裁判所の差止命令においてなじみのある基準を、緊急救済手続に当てはめる。救済は、それが認められなければ「直ちに回復不能の損失又は損害が生じる」場合に認められる。本規則38条は、一方当事者のみの手続参加による適用を認めない。申立当事者は、その申立てにおけるすべての他の当事者に通知しなければならない。選任に際して、緊急仲裁人は適切なスケジュールを立てるものとされ、それは「すべての当事者が審理を受けられる合理的な機会」を付与するものでなければならない。しかしながら、本規則が柔軟性を強調していることに従い、電話又はビデオによる審理が認められている。また、司法機関への暫定的措置の申立ては、本規則38条と「互換性がない」ものではなく、申立当事者の仲裁の権利の放棄ではないと本規則が明記している点は重要である。
終局的判断を求める申立て(Dispositive Motion)
新規則はまた、AAA手続における終局的判断を求める申立て(dispositive motion)の利用について対処している。本規則33条は、当事者が仲裁手続において終局的判断を求める申立てを行うことができる基準をまとめている。規則の下では、終局的判断を求める申立ては、当該「申立てがその事件における争点を処理し又は狭めることに成功する可能性が高い」ことを申立当事者が証明することができた場合にのみ、認められる。この高度な基準(司法手続には適用がない)は、本案において認められる可能性がほとんどない訴え却下の申立て、サマリージャッジメント(Summary Judgment)のための申立書、又はその他の終局的判断を求める申立てによって、当事者が時間と費用を浪費すること(そして仲裁手続が妨げられること)を回避する。
結語
10年間に渡り存在するAAA商事規則の初の改正は、アメリカの仲裁手続における実に大きな進展である。前記のとおり、この改正は実質的なものである。また、この改正は、何年にも渡って仲裁手続に浸透し、訴訟に代わる時間面・費用面で効率的な手段の国内第一の提供元であるというAAAの評価を脅かしていた訴訟手続から、仲裁を積極的に遠ざけるために考案されたものである。したがって、改正規則が適用される新たな仲裁に着手する前に、この新たな改正を研究して習得することは、仲裁に真剣に取り組む仲裁実務家(特に、仲裁を本質的に「会議室での訴訟」と捉えている者)の責務である。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com