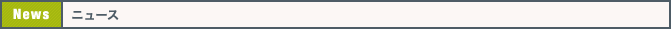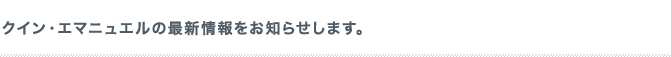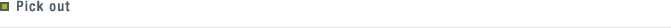お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
EU訴訟アップデート (17/09/20)
ドイツ:域外行為に対する特許権侵害責任の拡大
近時の決定において、ドイツ最高裁判所は、ドイツ国外の顧客に対して侵害製品を販売した外国企業の特許権侵害責任を拡大した。(2017年5月16日判決。ケースナンバーX ZR 120/15-Abdichtsystem)。
従前のドイツ判例法
外国企業からドイツの顧客に対する提供は、ドイツ国内において特許権侵害を構成する、との考え方が、最高裁判所の判例法において定立されてきた。(2002年2月26日決定。X ZR36/01-Funkuhr I)。この文脈においては、どこにおいてドイツの顧客が当該製品の占有を保持しているか(例えば、ドイツ国内なのか、海外なのか)、または、他の外国企業が最初の外国企業とドイツの顧客との間に関与しているかといった点は、最初の外国企業が当該製品は最終的にドイツ国内において製造を完了したものであると知っている場合は、無関係である。(2015年2月3日判決。ケースナンバーX ZR69/13-Audiosignalcodierung)。その結果、外国企業は、自らが、最終的にドイツ国内で製造を完了した特許権侵害製品を提供することについて明確な認識を有する場合には、ドイツ国内において特許権侵害責任を負うことになる。
本件
本件の被告は、今年の5月、その製品の大部分をドイツ国内では販売せず、主としてそれらをドイツ国外に本拠を置く顧客に提供すると決断した。しかしながら、これらの顧客の一部は、その後、これらの製品をドイツ国内において販売した。
原告は、第1審裁判所において、被告自身によるドイツ国内への提供を根拠として勝訴し、ドイツ市場からの当該製品の回収命令を含む解消措置が言い渡された。被告は控訴し、原告はその後ドイツ国内にて当該侵害製品を売却したドイツ国外の第三者に対する被告による提供についても事件を拡大するべく附帯控訴した。控訴裁判所(Oberlandesgericht Karlsruhe)は、被告の控訴と、当該附帯控訴をいずれも棄却し、従前の最高裁判所判決の流れに沿い、被告は、これらの第三者たる顧客がドイツ国内にて当該製品を販売することについての積極的な認識を持つ場合、ドイツ国内において当該顧客の行為を根拠とする責任を負うと判示した。しかしながら、控訴裁判所は、被告は、そのようなドイツ国内へのさらなる提供の可能性を考慮することができたにとどまり、それは明確な当該認識との関係では十分ではないと判断した。
最高裁判所の決定
控訴裁判所の決定を覆し、当該事件を差戻したうえ、最高裁判所はさらに進んで、以下のとおり判示した。ドイツ国内へのさらなる提供の明白な認識のみが責任を生じさせるのではない。加えて、供給者は、その顧客がドイツ国内へ当該製品を提供する可能性があるだろうと思われる十分な具体的事実が存在する場合においても、特許権侵害責任を負いうる。供給者は、その顧客による当該製品のさらなる使用を調査したり管理したりする義務を一般的に負うものではない。しかしながら、供給者は、その顧客のさらなる使用がドイツ国内への当該製品の提供による特許権侵害に繋がる可能性があると信じるべき具体的な理由がある場合、当該事案の状況を調査する義務を負う。しかしながら、それは、顧客がドイツ国内へ当該製品を提供するとの単なる抽象的な可能性では十分ではなく、それが実際にそういった事案となることを示す具体的な事実の存在が要求される。例えば、提供製品の量が非常に多く、特許による保護のない市場の範囲内においてのみ販売されるとは考え難い場合、そういった事案に該当する。このような状況下では、供給者は、その顧客がドイツ国内の特許権を侵害しないことについて、確信を持ちえない。事実、供給者は、事前の注意喚起の手段として、特許権侵害の可能性の有無を判別するため、顧客に対して、ドイツ国内における提供や勧誘について尋ねる義務を負う。仮に、当該顧客が満足いく回答を行わない場合において、供給者は、当該製品を当該顧客に提供し続ける場合には、その製品提供がドイツ国外にて行われている場合であっても、ドイツ国内における当該顧客の特許権侵害結果に加え、侵害者とみなされることになるだろう。
決定された事案においては、ドイツ国内へ提供された製品の合計数と、被告自身によってドイツ国内に直接提供された製品数の間に大きな差異があった。第一に、被告は、差止命令は、ドイツ国内における被告のビジネスに甚大な影響を与えるとも述べていた。それが判明したため、ドイツの顧客との実際の直接のビジネスは無視できた。ドイツ最高裁判所は、この陳述から、当該製品が被告の顧客によってドイツ市場に大量に納入されたはずであり、かつ、被告はこれらの事実を認識していたはずであると推論した。その結果、最高裁判所は、「ドイツ国内への提供について具体的な事実があることは否定しがたい」と判示した。
このような理由により、事案は、被告においてその顧客がドイツ国内に当該製品をさらに提供するだろうと信じるに足りる具体的な理由があったか否かという点を含む関連事実の調査のために、控訴裁判所に差し戻された。控訴裁判所は、被告の顧客らが、ドイツ国内に当該製品を提供することにより特許権を実際に侵害したか否か、または、少なくとも、第一次的な侵害のリスクが存在したか否か、という点についても調査しなければならないだろう。最高裁判所は、仮にそのような事案に該当する場合、被告は、ドイツ国内にて製造を完了していない製品を含むこれらの顧客に対する全ての販売実績を提供することにより、原告が被告の販売数を評価・確認するための対策をとれるようにする必要があるとも判示した。最後に、最高裁判所は、控訴裁判所に対し、それが何を伴うかについて多くの指針を提供することなく、差止命令を調整する際には、この特別の状況を考慮に入れることを課した。
結論
この決定は、ドイツ国内における特許権侵害について外国企業の責任を問う際には、当該外国企業がそれ自体直接ドイツ国内において活動することを要しない旨、示している。当該外国企業は、ドイツ国外を本拠とする顧客の活動について積極的な認識を持つ必要さえない。当該企業の顧客が、ドイツ国内へ当該製品を提供することにより特許を侵害している可能性を示す状況が、当該企業の責任を惹起するに十分なものとなり得る。それゆえ、当該企業にとっては、ドイツ国内におけるその顧客らの侵害行為を示す事実に気づいた場合にはすぐに、積極的に当該状況を調査し、当該顧客に対して特許侵害の可能性につき通知することが必須となる。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com