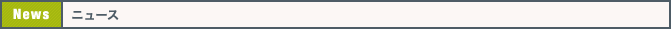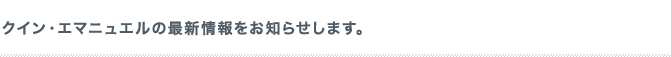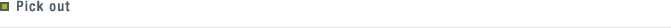お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
クラスアクションアップデート (18/10/11)
Epic Systems 事件におけるゴーサッチ裁判官の意見は、スカリア裁判官のようなクラスアクションに対する敵対心を示唆している
ヴァンダービルトロースクールの教授で、アントニン・スカリア裁判官の以前の書記官であったブライアンT.フィッツパトリックは、2017年のローレビューにおける記事において、「議会の行為がなければ、ルールの修正はなく、また(スカリア裁判官の)連邦仲裁法に関する意見以上に、クラスアクションの価値を下げる行政法規は存在しない」と記載した。スカリア裁判官の死、メリック・ガーランド裁判官への投票を上院民主党員が強制できない無能力さ、スカリア裁判官に代替する裁判官のオバマ大統領による指名、そしてニール・ゴーサッチ裁判官の指名と上院による承認に照らして、ゴーサッチ裁判官がスカリア裁判官のクラスアクションに対する敵対的な扱いを継続するか否かについて大きな関心が寄せられていた。そのような中、2018年5月に5対4の評決に基づきゴーサッチ裁判官により書かれた、Epic Systems Corporation対 Lewis事件判決は、彼がクラスアクションに対してスカリア裁判官と同様の姿勢を継続させることを強く示していた。
Epic Systems 事件における最高裁の判決は、3つの異なる訴訟から発生した。ロバート裁判長、ケネディ裁判官、トーマス裁判官、アリト裁判官を含む多数派を構成する5人のメンバーを代表して判決を書いたゴーサッチ裁判官は、3つのケースにおける争点について、「従業員と使用者は、両者間で発生したあらゆる紛争について1対1の個別の仲裁手続を通じて解決する旨を合意することは許されるべきか。または、従業員は使用者といかなる合意をしていたとしても、自らの請求を集団的又はクラスアクションにおいて行うことが許されるべきか。」と表現した。ゴーサッチ裁判官がどのように争点を表現したかを考慮すれば、5人の多数派メンバーが、従業員が個別の1対1の仲裁でいかなる労働紛争も解決すると同意した雇用条件を使用者において有効に主張することができる、と判断したことも驚きではない。
ブレイヤー裁判官、ソトメイヤー裁判官、カガン裁判官とともに、これに反対意見を唱えたギンズバーグ裁判官は、本件における争点について異なる見方をしていた。彼の争点の捉え方は、「連邦仲裁法では、賃金損失の補償を求めるときは従業員が単独でそれを行い、全国労働関係法によって従業員に保障されている、『相互扶助・保護のための共同行為に従事する』権利(全国労働関係法第157条)について考慮する必要はない、と使用者が主張することを許容しているか。」というものである(強調部分追加)。ギンズバーグ裁判官の表現が示唆するように、ゴーサッチ裁判官がその質問に対して肯定的な回答をする(つまり、全国労使関係局は使用者が労働紛争における1対1の仲裁を求めることを禁止していない、と解釈すること)にあたって直面する一つの難関は、ギンズバーグ裁判官が自らの質問の中で指摘した強調された引用部分である。
ゴーサッチ裁判官は、相互扶助・保護のための共同行為に対する全米労働関係委員会による法律的な保護が、なぜ仲裁においてクラスアクションを起こす権利を保障しないのかという問題点について、ラテン語で「同類の」という意味を持つ、「ejusdem generis」という解釈基準を用いることで解決を図った。その基準によると、法律が同種の権利を複数列挙し、その後に異なるタイプの権利を合理的に暗示できるようなより一般的な言語を含むときは、追加で保障される権利は具体的に法律で列挙されている権利と同種の権利に限られることになる。Circuit City Stores, Inc. 対 Adams事件(2001)参照。全国労働関係法が労働者に保障する「団体交渉又はその他の相互扶助・保護を目的としたその他の共同行為に従事する」という表現は、団結権や団体交渉に関連した保護の後に続いて書かれている。したがって、ゴーサッチ裁判官は下線部で強調された表現は、「その他」の団結権や団体交渉行為に限定して適用されるのであって、従業員に共通する賃金請求に関するクラスアクションを行うために結束することには適用されないとした。これに対して、ギンズバーグ裁判官は、ゴーサッチ裁判官の「ejusdem generis」に基づく分析に対して「著しい欠陥がある」と断じた。
ゴーサッチ裁判官は、連邦裁判所によって是認され、75年来の全米労働関係委員会の決定で確立されている、同委員会による広範な言語である、「全米労働関係委員会は、使用者によるクラスアクションの権利行使を諦めることの要求から従業員を保護する」、という同委員会における汎用性の高い表現についてどのように切り抜けるか困難に直面した(ギンズバーグ裁判官は、上記判断を示した同委員会及び連邦裁判所の1942年、1943年、1964年、1973年、1980年、1982年、2005年及び2011年における判決を引用している)。これと同様に、最高裁判所判決で採用された「相互扶助」という表現が「行政や司法の場によって労働条件の改善を求めようとする従業員」にも適用される、という解釈を乗り越えることにもゴーサッチ裁判官は苦労していた。ちなみに、上記解釈については、(Eastex, Inc 対 NLRB事件判決(1978年)を引用しながら)「傍論」としてゴーサッチ裁判官はこれを却下している。
ゴーサッチ裁判官のEpic Systems事件における判決は、クラスアクションの範囲を限定する結果に至るという点だけでなく、自信に溢れ、雄弁で、かつ好戦的なトーンを採用しているという意味においても、スカリア裁判官のクラスアクションに関する司法解釈と同じ道をたどっている。スカリア裁判官と同様に、ゴーサッチ裁判官は、巧みな言い回しを利用して(「但書によってもなお請求原因は成り立たない」)、原告の主張や反対意見を牽制している(「この主張は高い壁に直面している」、「多くの終末論的な警告と同様に、この警告は誤りである」)。Epic Systems事件における判決は、スカリア裁判官のクラスアクションに関する司法解釈がまだ有効であり、ゴーサッチ裁判官が法廷においてスカリア裁判官の代理人として機能していることを示している。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com