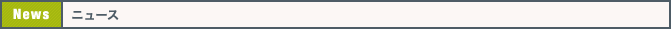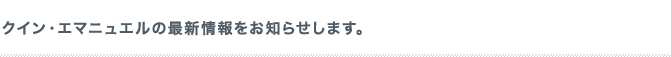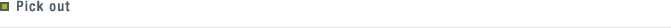お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
最高裁は、外国人不法行為請求権法の下では外国会社は責任を負わないと判断 (18/11/15)
2018年4月24日、アメリカ最高裁はJesner 対Arab Bank事件において、待望の判決を下した。最高裁は、結論として、外国人不法行為請求権法(ATS)は外国会社を相手方とする提訴権を与えていないと判断した。その判断において、最高裁は、外国会社、特にアメリカ国内に籍を置き、国際法違反行為に対する有効な民事回復手段を欠く外国会社に対して、少なくとも仮救済の請求原因を与えた。
以前に、Kiobel 対Royal Dutch Petroleum事件において、クインエマニュエルは最高裁で9人満場一致となる画期的な判決を取得した。その判決は、ATSはいわゆる”foreign cubed”ケース、すなわち原告、被告及び問題となる行為全てが外国で起きたケースに対して、領域を越えては適用されないという内容となっている。Jesner事件で、最高裁はKiobel事件で未解決のまま残った争点、つまり会社はATSの下で責任を負うのかという点について、責任を負わないと確認することで確実に解決したといえる。
1789年に裁判所法が制定されてから、ATSは外国人に対して「アメリカの法律や条約に違反して行われた」不法行為について、民事訴訟を提起する管轄を与えた。1980年以前はこの法令が使用されることはまれであったが、ATSは海外における人権侵害(よく主権免責を有する外国政府によって行われる)を主張する原告に代わって提訴することを模索する公共団体にとって、人気の手段になった。Kiobel事件では、連邦地裁はATSは会社に対する提訴を認めず、原告の請求を退けるという判断をした。連邦第2巡回区控訴裁判所がそれを是認した後、最高裁は、”foreign cubed”ケースにおいてATSは領域を越えて適用されないという異なる理由を採用したものの、満場一致でクインエマニュエルのクライアントに有利な形で同控訴裁判所の判断を是認した。しかし、最高裁は、”foreign cubed”の事実背景を離れて、会社がATSの下で提訴され得るのかという点については検討しなかった。
Jesner事件では、ハマスに起因するテロ行為の被害者が、主要なヨルダンの銀行であるアラブ銀行をニューヨークの連邦地裁南部地区で提訴した。原告は、アラブ銀行が(i)クリアリングハウス銀行間支払システムによるドル建ての取引決済、及び(ii)テキサスを拠点とし、原告がハマスと提携関係にあると主張するHoly Land Foundation for Relief and Developmentのためのマネーロンダリングを通じて資金集めを促進することによってハマスと共謀したと主張した。原告はさらに、アラブ銀行は上記2つの行為の一部をニューヨーク支店を通じて行ったと主張した。会社に対する提訴を禁止するKiobel事件の第2巡回区控訴裁判所の中間判決は、異なる理由で最高裁に是認されたが、会社はATSの下では訴訟の対象にならないという同裁判所の判断内容は同巡回区で支配的な前例として残っていた。したがって、連邦地裁はJesner事件を却下し、第2巡回区控訴裁判所はそれを是認した。
Jesner事件はKiobel事件で未解決のまま残った会社のATS上の責任に関する論点を提起したが、ケネディ裁判官の意見の中で最高裁の過半数を占める5人の裁判官は、外国会社はATSの下では責任の対象とはならないという判断を示した。裁判所がこの結論に至ったのは、ATSは外国との関係を改善するという目的のもと、謙抑的で適用範囲も狭いと考えたこと、及びATSを外国会社を相手方とした場合の救済手段を提供するものと拡大して適用することは裁判所よりも議会がより適切であると考えたことにある。それゆえ、裁判所はJesner事件の事実関係に照らして、裁判所がATSの責任を外国会社にまで及ぼすことは不適切であると判断した。
最高裁は、第2巡回区控訴裁判所がKiobel事件でATSの責任はいかなる会社との関係でも排除されると判断したところまで踏み込んではいないが、Jesner判決はなお重要な意義を有している。
第一に、Jesner判決は明らかに国際法違反における外国会社の責任に関する問題を議会に付託した。議会において、ATSを外国会社に対する提訴を許容するように明確に修正しない限り、そのような提訴は禁止される。Kaplan対 Cent. Bank of the Islamic Republic of Iran事件(Hezbollahによるロケット攻撃のための資金集めをしたとされるイラン銀行に対するATSに基づく主張の却下を是認した)、Wildhaber 対 EFV事件(スイス政府当局に対する原告の主張を却下した)参照。
第二に、Jesner判決は、第2巡回区控訴裁判所がKiobel事件で判断したように、国際的な人権基準は自然人にのみ適用され、会社には適用されないということを示唆した。Jesner事件(「国際社会」は従業員の行為に対する会社の責任についてまだ全世界的に受け入れたわけではないと指摘した)、Kiobel事件(最初から、国際法違反に関する個人責任の原則の適用は、会社などの法人ではなく、自然人に限定されていた。なぜなら、犯罪に関する道義的責任を「国際犯罪」というレベルにまで押し上げるのは、それを犯した個人の男性や女性に唯一かかっているからである)、The Nurnberg Trial事件(国際法に違反する犯罪は、抽象的な存在によってではなく、人によって遂行される。そして、その犯罪を犯した個人を処罰することによってのみ、国際法の条項は強制しうる)参照。連邦裁判所は、会社それ自体に対する訴訟に代えて、会社の役員や取締役に対するATS訴訟の可能性を見出しているかもしれない。
第三に、外国会社に対する人権訴訟は、イギリスやEUなどのより保護の手厚い法廷に移行する可能性がある。同様に、人権提唱者は州法に基づく主張を試みるかもしれない。また人権提唱者は、反テロリズム法のような他の連邦法に基づき外国会社を提訴できるアメリカ市民に焦点を当てるかもしれない(国際的なテロ行為によって傷害を受けたアメリカ国民は連邦裁判所に3倍の損害回復を求めて提訴できるという条件の下で)。
第四に、Jesner判決は他の背景において外国のポリシーが関わってくる主張を避けるように裁判所を促す可能性がある。例えば、第9巡回区控訴裁判所で反対意見を唱えた裁判官は最近、メキシコでメキシコ人の若者を射殺したとされているアメリカの国境パトロールに対する民事的な損害回復について裁判所が暗示してはならないと主張するためにJesner判決を頼った。City of Oakland 対BP P.L.C.事件参照(地球温暖化に基づく石油会社に対する公的不法妨害に関する主張を退けるにあたって、「外国のポリシーに関する事項について検討する組織的な能力と責任があるのは、司法ではなく、政府である」というJesner判決における指摘を引用した)。
最後に、裁判所は、不適切に提訴権を作出したり、裁判上認められた提訴権を拡大したりすることを避けるため、ATS及びその他の連邦法を保守的に解釈するにあたってJesner判決を頼りにする可能性がある。Nahl 対Jaoude事件(マネーロンダリングが国際法違反ではないこと、「連邦裁判所はATSにおいて新しい形態の責任を認める前に重大な注意を払わなければならない」という原則を採用するJesner判決を引用して、Hezbollahのためのマネーロンダリングを根拠とするATSに基づく主張を却下した)、Kirtman対Helbig事件(Jesner判決で指摘された最高裁の「裁判上の提訴権拡大に対する一般的な謙抑性」に一部頼ることによって、囚人に対する報復を理由とする米国憲法修正第一条の権利行使に関するBivens事件における請求原因を否定した)参照。
したがって、Jesner判決は、外国会社に対するATS上のクレームを排除するだけでなく、より一般的に連邦裁判所におけるATS訴訟に関する減殺された役割を示している。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com