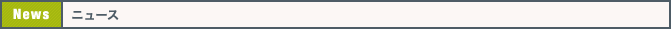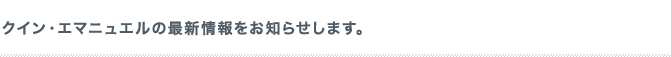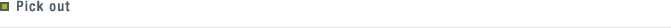お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
巡回裁判所の見解の相違、
商標権侵害訴訟の結果に影響を与える (20/01/30)
商標権侵害訴訟においては、訴訟を提起する、もしくは訴えられる際の場所によって訴訟の解決方法に大きな違いがあらわれる。巡回裁判所(特に第二と第九)は商標権訴訟において、商標の不正使用が映画やテレビ番組のような*¹独創的な表現作品においてなされた場合に米国憲法修正第1条(◇宗教・言論の自由)をいかに解するべきかについて見解が割れている。巡回裁判所はさらに原告が被告が故意に行動したことを示さずして被告が享受した利益をうけてもよいのか否かについても見解が割れている。最高裁判所が次法廷開催期にこの見解の相違に取り組もうとするだろう。
1980年代の後半には第二巡回裁判所は、表現作品の題名が偽造の広告であると申し立てられている際に、米国憲法修正第1条(◇宗教・言論の自由)と連邦商標法とを比較考慮するためのテストを作った。ロジャーズvsグリマルディの裁判(Rogers v.Grimaldi)で第二巡回裁判所は、商標権の使用は以下の場合において、米国憲法修正第1条(◇宗教・言論の自由)により保護されるとした。題名が(1)「作品に少なくとも何らかの芸術的な関連性」があること。そして(2)「作品の内容に関して明らかに需要者に誤解をいだかせる」ようなものでないこと。Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 1000-01(2d Cir. 1989) 第二巡回裁判所は後にこの枠組みを商標権侵害の主張に適用した。E.g., Twin Peaks Prods., Inc. v. Publ’ns Int’l, Ltd., 996 F.2d 1366, 1379 (2d Cir. 1993) 第九巡回裁判所を含む他の巡回裁判所は、それ以降独創的な表現作品に基づく商標権侵害の主張に対しては、ロジャーズテストを採用してきた。
しかし、第二巡回裁判所と第九巡回裁判所はロジャーズテストをその意味を異ならせて適用する。第二巡回裁判所が商標権侵害訴訟においてロジャーズテストの使用を採用した際、裁判所は表現作品における商標の使用が需要者に明らかに誤解を与えるようなものであるか否かは、「第一審で高徳なポラロイド(登録商標)要因(Polaroid factors)の適用をすることで行わなければならない」とした。Twin Peaks, 996 F.2d at 1379
第二巡回裁判所はさらに、混同のおそれが「特に避けられないもの」である場合、「明らかに誤解を招く」という要件は満たされるとした。
同様に第二巡回裁判所では権限を与えられたなされた商標権の使用が、通常の商標権訴訟において、混同を招きかねないのか否かを判断するのと同じ8つの要因がそのような使用が明らかに誤解を招くものであるのか否か、そしてその上で独創的な表現作品の文脈において起訴できるのかどうかといったことについても影響をもつ。
対照的に、第九巡回裁判所は明らかに誤解を招く質問を混同のおそれテストとは別の離れた基準の要件として扱う。
したがって、その使用が明らかに誤解を生むものであると判断するために第九巡回裁判所は「明らかな兆候」「公然の主張」、もしくは「明白な虚偽の申し立て」があることを要求する。Twentieth Century Fox Television v. Empire Distrib. Inc., 875 F.3d
1192, 1199 (9th Cir. 2017) 商標権侵害の原告は第二審にてこの基準に合致する必要はないが、かわりに表現作品での商標権使用によって生まれる、特に避けられない混同のおそれがあることを示さないといけない。
しかし、第九巡回裁判所は混同のおそれについての要因は、表現作品における商標権使用が明らかに誤解を招くものであるのか否かについてとは無関係であるとしている。
巡回裁判所はさらに、商標権侵害訴訟の原告が被告が享受した利益を得る前に被告が故意の侵害をしたということを法(15 U.S.C. § 1117(a))の下、証明しないといけないのか否かについても見解が割れている。
その法典は利益をうけることを「公正性の原則の問題」として認めている。 多くの裁判所はこれを、コモンローにおける故意の要件を組み込んだものとして解釈したが、その他の裁判所は原告に利益を享受する権利があるのか否かを判断するために多くの公正な要因を探した。参照. Id.; see, e.g., Quick Techs. v. Sage Grp. そして以下に含まれる要因を検討した。(1)被告に混同させる、もしくは騙す意図があったか否か(2)売り上げが流用されていないか (3)その他の救済策の妥当性(4)原告が己の権利を主張するまでのすべての不当な遅れはあったか(5)不正行為を不利益的とすることに関する公共の利益(6)詐称の訴訟ではないか
商標希釈訴訟においての報酬の付与の認定には「故意の侵犯」が要求されるということを明らかにするために議会はセクション1117(a) (Section 1117(a)) を1999年に改正した。裁判所らはそれ以降議会が希釈の申し立てに関しては故意の要件の包含を明示するものの、一方で同様の要件を商標権侵害においては含めないことは、商標権侵害において故意の要件を否認していると解釈すべきか否かとの論題に取り組んできた。
合衆国連邦巡回区控訴裁判所は最近この見方をRomag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 817 F.3d 782, 789 (Fed. Cir.2016) ロマグ訴訟において、セクション 1117(a)が利益の承認が「公正性の原則の支配下にある」ことを要求しているために、故意は商標権侵害において必要要件でいまだあるとして退けた。
裁判所は改正は「1960年の希釈法にあった誤りを正すため」に行われたものであり、故意の要件を入れることは、希釈訴訟において故意は常に要求されるものの、侵害訴訟においてはその限りでないとの、主張の一部否認という現象を作り上げはしないと根拠づけた。
最高裁判所はロマグ訴訟において移送命令を下し、セクション1117が原告に商標権侵害者が享受した利益を得る前に故意をもって行動したことを証明することを要求しているのか否かを判断する。それまでは、巡回裁判所は故意が認定に必要であるか否かについては見解が割れたままである。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com