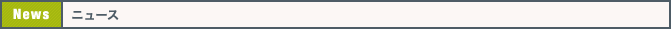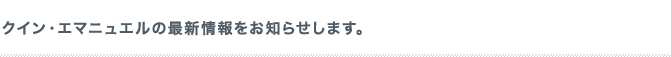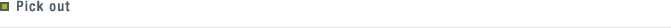お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
統一特許裁判所と単一効特許制度の概要 (23/03/24)
統一特許裁判所(以下、「UPC」)は、2023年6月1日に開所することを表明した。 この日から、ユーザはUPCの電子事件管理システムにより訴訟の提起を開始することができる。 欧州特許庁(以下、「EPO」)は、UPCを単一効特許とともに、より強力で一元的、かつ費用対効果の高い欧州特許制度の基礎となる要素として推進してきた。単一効特許は、EPOへの一度の申請で最大25の欧州連合加盟国での特許保護を可能にすることで、特許申請プロセスの簡素化とコスト削減を目的としている。UPCは、参加する欧州連合加盟国の侵害および有効性に関する紛争を判断する共通の裁判所として機能することで、費用のかかる並行訴訟をなくし、法的確実性を高めることを目的としている。また、UPCは、よりシンプルで迅速、かつ効率的な司法手続を提供することを目的としている。UPCと単一効特許を含む新しい欧州特許制度への移行は、7年間の移行期間があり、さらに7年間延長される可能性があるため、長期にわたるものとなるが、今後数ヶ月の間に発効する即時の変更もあり、その考察の実施が重要となる。
I. 歴史
1977年以来、EPOは特許を付与するための単一の一元的なプロセスを提供してきた。しかし、EPOは欧州特許権を有効化し、保護するための単一で一元的な情報源を提供していない。その代わりに、EPOによって付与された特許は、それが効力を発揮する各国において有効化および維持されなければならず、それぞれが独自の法律と手続きを適用する各国の裁判所においてのみその特許権行使が可能である。このような各国での権利行使は、財政的な観点から非現実的であるだけでなく、訴訟結果に一貫性がなくなる可能性がある。欧州連合理事会と欧州議会は、欧州連合における単一効特許保護の基礎を築くために2つの規則を採択することで、こうした非効率性への対応を推進した。
2013年2月19日、統一欧州特許裁判所に関する協定(以下、「UPC協定」)が、ほとんどの欧州連合加盟国によって署名された。UPC協定は、これまで各国の裁判所で個別に特許権の権利行使をしていたものを、UPCを通じて全加盟国で同時に行使できる単一効特許に道を開くものである。 UPC協定の発効にはドイツ、フランス、イタリアを含む13カ国の批准が必要であった。 それから約10年、2023年2月にドイツがUPC協定の批准書を寄託することで、ようやくこの要件が達成され、2023年3月1日にサンライズ期間が開始される見込みとなった。現在までに17カ国がUPC協定を批准しており、批准しているのはオーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンである。 (イギリスは2020年7月20日のEU離脱(ブレグジット)により批准を取り下げた)以前にUPC協定に署名した7つの追加の欧州連合加盟国に関しては、いつでも批准を選択することができる。
II. 単一効特許
単一効特許は、今のところ「従来型の」欧州特許に取って代わることを意図したものではなく、特許権者に新しい選択肢を提供するものである。単一効特許は、「統一的な効力を持つ欧州特許」と説明されており、欧州特許条約の規則と手続きに基づいてEPOが付与する従来型の欧州特許として発行される。その後、17の批准国の特許権者は、特許付与の公告から1ヶ月以内に、EPOに対して付与後手続を開始し、統一的な効力を要求することができる。すべての要件が満たされた場合、EPOは欧州特許に対し単一効特許を登録する。単一効特許は、批准国のすべてにおいて一括で制限、譲渡、無効化、または失効することしかできない。また、単一効特許はUPCの専属管轄権に服することになる。発明者は、統一的な効力を持たない従来型の欧州特許に関してはEPOに、また、国内特許に関しては各国特許庁へと引き続き出願をすることが可能である。
単一効特許の主な目的は、EPOが単一効特許の管理のためのワンストップ・ショップとして機能するようにすることである。単一効特許の取得、維持、管理は、多数の国家機関ではなく、単一の組織で行うことができるようになる。
単一効特許制度は、UPCが開所する日と同じ2023年6月1日に開始される予定だ。この日から、欧州連合の2つの規則が適用され、EPOに単一効特許の管理を正式に委託する「単一効特許保護に関する規則」が施行される。(欧州特許庁のウェブサイト(https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a41.html)にて、単一効特許保護に関する規則が公開されている) しかし、単一効特許の普及を促進するため、EPOは2つの経過措置を導入し、より早く出願ができるようにした。最初の経過措置は、特定の出願人が2023年1月1日から統一的な効力を早期に請求することを認めるものである。統一的な効力登録の要件が満たされれば、2023年6月1日に単一効特許制度が開始された時点で、EPOは統一的な効力を登録する予定である。同様に2023年1月1日から始まる第2の経過措置は、欧州特許庁によるEPC規則71(3)に基づく通知の発行後、欧州特許が単一効特許保護の対象となるように、付与を意図した文章を承認する前に、出願人が欧州特許の発行を延期することを認めるものである。
III. 単一効特許保護の出願に関する留意点
EPOが推進する単一効特許の主な利点は、コストの削減である。このようなコスト削減は、有効化、更新、および翻訳プロセスに関連して実現することができる。 従来型の欧州特許がEPOによって付与されると、その保護を求めるすべての国の国内特許庁を通じて特許の有効性を確認する必要がある。有効性確認の費用には、各国特許庁ごとに異なる有効性確認費用と、その国特有の有効性確認規則を理解するために必要な弁護士やその他のサービス提供者らが請求する費用が含まれる。単一効特許システムでは、単一の訴訟がすべての参加国での保護を提供する。同様に単一効特許システムは、単一効特許の更新を一元化し、2015年にドイツ、フランス、イギリス、オランダへと支払うべき更新料の合計に相当する単一の更新料が欧州特許庁に支払われるが、従来の欧州特許の場合だと更新料は各国特許庁に支払わなければならない。 また、翻訳要件や翻訳料に関しても削減される。単一効特許制度では、単一効特許を出願する際に出願人は、英語または欧州連合加盟国の他の公用語による欧州特許の全訳1つのみを提出しなければならない。 欧州特許庁は、その存続期間中に単一効特許は、従来の欧州特許よりも3,680ユーロ安くなると推定している。 (コスト試算の詳細は、こちらにて閲覧可能:https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html)
しかし、コスト削減のメリットは、以下に述べる単一効特許システムの他の効力とともに総合的に考慮する必要がある。そのような効力の1つは、単一効特許がその有効性に関する一元的な攻撃(セントラルアタック)に対して脆弱であることであり、 従来型の欧州特許は、ある1つの国でその異議申し立てに成功したとしても、他の国ではそれによる法的効力はないが、単一効特許は一つの訴訟によって17カ国すべてで特許が無効とされる可能性がある。単一効特許システムの統一的な性質は、特許権者が異なる国で特許を異なるように構成する柔軟性を低下させる可能性もある。現行の欧州特許制度では、特許権者は、競合する国内特許権者による異議申立のリスクを軽減するために、特定の国でのクレームを戦略的に除外することや、特定の国での登録を完全に回避することができる。このような柔軟性は、単一効特許制度では得られない。
IV. 統一特許裁判所
単一効特許と同様に、UPCは、現在侵害訴訟や有効性訴訟を審理している国内裁判所に取って代わるわけではなく、国内裁判所は従来通り業務を継続することになる。むしろ、今のところ、UPCは侵害訴訟と有効性訴訟のための新しい国際裁判権を提供するものであり、現在侵害訴訟と有効性訴訟を審理している国内裁判所の代わりとなるものではない。またUPCは、単一効特許に関連する訴訟の専属管轄権を有することにもなる。
V. 統一特許裁判所の構造
UPCには、第一審裁判所と控訴審裁判所の2つの階級がある。第一審裁判所は、中央部、地方部、地域部の3部構成となっている。中央部はパリに本部を置き、ミュンヘンに第二本部を置く。第一審裁判所は、無効訴訟と非侵害訴訟を審理する。また、侵害訴訟に関しても一定数審理することがある。地方部はウィーン、ブリュッセル、コペンハーゲン、ヘルシンキ、パリ、デュッセルドルフ、ハンブルク、マンハイム、ミュンヘン、ミラノ、ハーグ、リスボン、リュブリャナに所在している。地方部は、侵害訴訟および無効の反訴のための主要な場となる。地域部は、2つ以上の欧州連合加盟国に対して設置することができる。現在、ストックホルムを拠点とする、スウェーデン、エストニア、リトアニア、ラトビアを対象とする北欧バルト地域部があり、リガ、タリン、ビリニュスにも設置されている。控訴審裁判所はルクセンブルグに拠点を置いており、第一審の判決に対する控訴への判決を下す。
2022年10月19日にUPCは、法律系判事と技術系判事の2つの任命区分で85人の判事の任命を発表した。法律系判事34名は特定の裁判所や場所に配置され、技術系判事51名はバイオテクノロジー、化学・薬学、電気、機械工学、物理学の5つの技術分野に任命されている。中央部では、異なる加盟国から来た2人の法律系判事と1人の技術系判事で構成される3人の判事パネルが訴訟を審理する。地方部と地域部も3人の判事で審理を行い、3人の法律系判事、そして必要な場合には4人目の技術系判事で構成される。技術系判事の多くは、個人営業を行っており、パートタイムの判事として出席することになる。
VI. UPCの管轄権とサンライズ期間
2023年6月1日にUPCが開所すると、欧州特許、特許出願、補足保護証明書は、既定事項としてUPCの管轄下に置かれることになる。これにより特許権者は、UPCで権利行使のための訴訟を1つ起こすことにより、批准している加盟国内で欧州特許を行使できるようになる。またこれは、欧州特許がUPCへの単一の提訴によって無効化される可能があることをも意味する。ただし、欧州特許、出願書、補足保護証明書の保有者は、それら特許をUPCの管轄から外すことができるが、それらがUPCの管轄にならないよう確実にするには、サンライズ期間中にこれを実施する必要がある。 特許がUPCにおける訴訟の対象になっていない限り、2023年6月1日から始まる7年間の経過措置期間中も、オプトアウトのオプションは利用可能だ。この経過措置期間は、さらに7年間延長することができる。特許権者は、代理人としての登録実施後に、UPCのケースマネジメントシステムを使用して特許をオプトアウトする必要がある。オプトアウト後、UPCは本出願、特許、補足保護証明に関連するいかなる訴訟についても管轄権を有しない。ただし、オプトアウトは、出願、特許、または補足保護が国内裁判所に対する訴訟の対象になっていない限りはいつでも撤回することができる。特許権者がオプトアウトを撤回した後、特許権者は2回目のオプトアウトを行うことはできない。移行期間終了後は、欧州特許、出願、補足的保護証明書をオプトアウトすることはできなくなる。
VII. オプトアウト・オプションの効力
オプトアウトを選択することで、UPCにおける単一の無効訴訟において、特許がより容易かつ効率的に国を超えて無効化される可能性を防ぐことができるため、特定の特許権者は防衛手段としてオプトアウトを選択するかもしれない。オプトアウトする他の理由には、未知の法的環境でその特許が試されることへの特許権者の恐怖も挙げられる。一方、コスト意識の高い特許権者は、単一の訴訟で特許を無効化から守ることができることにメリットを感じるかもしれない。
また、戦略的にオプトアウトし、その後オプトアウトを撤回することも可能であろう。例えば特許権者は、UPCにおける一元的無効訴訟から身を守るために特許のオプトアウト状態を維持し、その後オプトアウトを解除してUPCで侵害訴訟を提起し、より低いコストとより効率的な手続きの恩恵を受けることができるかもしれない。しかし、このような戦略の利点は、2回目のオプトアウトを禁止する規則だけでなく、UPCで提起された侵害訴訟は、訴訟中の特許をUPC配下での無効の反訴にさらすために制限される。さらに、国内裁判所に提起された無効訴訟は、再度オプトインすることを不可能とする。
VIII. 想定される裁判管轄の問題
UPCは2023年6月に開業するが、解決しなければならない多くの管轄権に関する課題があると考えられ、共通の裁判所という目標を達成するのは何年も先のことであるように思われる。移行期間中に欧州特許は、UPCと国内裁判所の両方で訴訟の対象となる。(ただし、並行手続きはそうではない)同様にオプトアウトされた特許は、移行期間中、少なくとも7年間、場合によっては最長14年間、異なる国内裁判所ごとの相反する可能性のある判決にさらされ続けることとなる。この判決には、相反する可能性がある無効化の判断、侵害の認定、FRANDの料率や条件などが含まれる。移行期間が終了した後も、UPCに代わる裁判所が存在する可能性がある。例えば、欧州特許機構には、UPC協定に批准していない、または批准しない可能性のある加盟国が存在し続ける。スペイン、ポーランド、クロアチアは全て、UPC協定に署名していない欧州連合加盟国である。また、イギリスは欧州連合から離脱したために批准を取り下げている。スイスとトルコは欧州連合に加盟していないため、批准の選択肢はなかった。したがってこれら6カ国は、欧州特許条約の加盟国であり、欧州特許での指定が可能であるにも関わらず、すべてUPCの管轄外なのである。指定国とは、欧州特許出願人が特許出願の際に、発明の保護を求める国として記入する国のことだ。 締約国とは、欧州特許条約に批准し、欧州特許機構に加盟している国だ。これらの国がUPC協定に加盟し続けない場合、特許の有効性に関するUPCの裁定はこれらの国には自動的には適用されない。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com