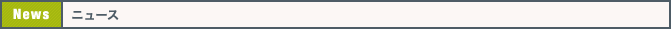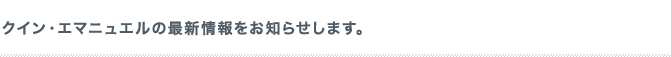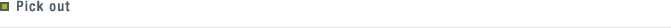お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
特許法下での侵害品の輸出 (23/05/26)
特許法は、国内活動(35 U.S.C. 第271条(a)~(c)参照)及び外国活動(同 第271条(f)参照)の双方に関して、侵害訴訟を起こすことを認めている。 前者には特許発明の「米国内での」製造、使用、販売又は輸入が含まれ、後者には「米国外で」最終的に組み立てるために、発明の組み立て前の部品を輸出することが含まれる。 注目すべきは、特許訴訟の大半は、同法の国内侵害条項のみに基づいて提起されていることである。 Daniel Moffett, et al., Overlooked Patent Cases: Foreign Activity Liability, Damages, Law360 (Sept. 30, 2021)を参照。 例えば、過去3年間で、第271条(f)は全ての法域でたった4件の公表済み判例に引用されただけであるのに対し、271条(a)~(c)は100件以上の公表判例で引用されている。この傾向には、いくつかの理由がある―例えば、特許権者が権利の上に眠っている可能性や、一方でリスクを回避したい競合他社が特許権の範囲を過大評価している可能性など―が、すべては共通のテーマに帰結するように思われる:利害関係者は 第271 条(f)に関する十分な情報を持っていない。同上;Katie E. Hyma, Legislative Ballast: The Case for Repealing 35 U.S.C. § 271(f), 69 Syracuse L. Rev. 155, 183 (2019) を参照。 本稿は、関連する歴史と第271条(f)に基づく法律の現状を概説することにより、この問題を対象とする。 米国における製造活動の歴史的な復活に向けて、政治的・経済的な力が収斂しており、国内製品の輸出に関わる特許法の規定を理解することは、かつてないほど重要なことかもしれない。
I. Deepsouth 判決の抜け穴を防ぐ
特許法第271 条(f)に対するいかなるアプローチにも、その法制上の発端を理解することが必要である。 実際、最高裁は、その範囲を解釈するために、何度もこの規定の「歴史」と「意図」に依拠してきた。 Life Techs. Corp. v. Promega Corp., 580 U.S. 140, 151-52 (2017)。これは、第271条(f)が、議論を呼んだ最高裁判決、Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972)に対する直接的な立法の対応であったためと考えられる。
Deepsouth 判決は、エビの殻剥き機をめぐる紛争を扱った。 被疑侵害者であるDeepsouth社は、同機械が米国内で製造又は使用された場合には、訴訟対象となっている特許権を侵害することは争わなかった。 しかし、Deepsouth社は、米国特許法のいかなる規定も、その機械の組み立て前の部品を製造し、最終的な組み立てのために海外に出荷することを妨げるものではないと主張した。 裁判所はこれに同意した。 Deepsouth社も、その海外の顧客も、特許発明を「米国内」で製造、使用又は販売していたものではなく、当時はこれらの行為が特許法が禁止していた全てであった。そもそも、同機械の発明の対象はあくまで完全に組み立てられた製品であり、その部品ではなかった。そして、完全に組み立てられた製品は外国で完成されたものであるため、特許法の適用範囲外であった。 この理由は、今日では「Deepsouth 判決の抜け穴」として知られており、この判決を事実上覆す271条(f)の制定に直接繋がった。 Promega Corp. v. Life Techs. Corp., 773 F.3d 1338, 1352 (Fed. Cir. 2014) (「271条(f)はDeepsouth 判決の「抜け穴」を閉じた」)を参照。 最高裁が最近説明したように、同(f)は、「米国で製造されるが海外で組み立てられるものであり、以前の法設計では法律の及ばないところにあった、部品を対象とすることによって、特許権の行使可能性におけるギャップを埋めるものである」。Life Techs., 580 U.S. 151-52頁。 したがって、今日この規定を解釈する際は、裁判所は、提示された解釈がその議会の「意図」に「合致」しているかどうかを検討する。同上。
II. 第271条(f)の文言
文言上、第271条(f)は、“特許発明の部品を米国から供給することを含むよう侵害の定義を拡大” することにより、Deepsouth 判決の抜け穴に対処した。WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S. Ct. 2129, 2134 (2018)。 したがって、国内での組み立てはもはや要件ではない;被疑侵害者が海外で最終的に組み立てるために、発明の組み立て前の部品を供給した場合、十分である。この規定は、「異なるシナリオに対処することで連動する 」二項を通じて運用される。 同上。 「第271条(f)(1)は、発明の構成要素の[全て又は]相当部分を輸出する行為に対処するものであり、第271条(f)(2)は「発明のために特別に適合させた構成要素を輸出する行為に対処する」。 同上、2134-35 頁。全文を読むと、この規定は以下のとおりである:
(1) 特許発明の全部又は相当部分の構成要素の全部又は一部が組み立てられていない場合に、米国内で組み立てた場合には特許を侵害するような方法で、米国外で当該構成要素の結み立てを積極的に誘発するように、権限なく、当該構成要素の全部又は相当部分を米国内で又は米国から供給し又は供給させる者は、侵害者としての責任を負うものとする。
(2) 特許発明の構成要素の全部又は一部が組み立てられていない場合に、その発明における使用のために特別に製造され又は特別に適合された部品(実質的に侵害しない使用に適した商用の汎用品または代替可能品は除く)について、当該構成要素が特別に作られ又は適合されていることを知りながら、当該組み立てが米国内で生じた場合には特許を侵害するような方法で米国外でも組み立てることを意図して、権限なく、当該構成要素を米国内で又は米国から供給し又は供給させる者は、侵害者としての責任を負うものとする。
特許法の間接侵害規定である第 271 条(b)及び(c)をよく知る方は、多くの重複があることに気づくだろう―実際、第 271 条(f)は意図的にこれらの規定の「文言を模倣」している。 Zoltek Corp. v. United States, 672 F.3d 1309, 1334 n.6 (Fed. Cir. 2012) (Dyk., J., dissenting)。立法経緯が明らかにしているように、「(f)(1)の『積極的に誘発する』という用語は、現行の第271条(b)から引用されている」し、「(f)(2)の『使用のために特別に製造され、又は特別に適合された』と読む箇所は、現行の第271条(c)から来ている」。Section–by–Section Analysis of H.R. 6286, 130 Cong. Rec. 28069 (1984); Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 550 U.S. 437, 445 (2007) (Section-by-Section Analysisを引用している) も参照。 しかし、271 条(f)と間接侵害の規定との間には、重要な相違点もある。 例えば、271 条(f)(1)は、発明の構成要素の全部又は相当部分の供給のみに適用されるため、(b)より狭くなっており、例えば専門知識や相談の提供に対する責任は除外される。3 Moy's Walker on Patents § 12:29 (4th ed. Dec. 2020 Update)。同様に、第271 条(f)(2)は、(c)と異なり、侵害する組み合わせを 「米国外」で組み立てるという具体的な意図を要求する。同上。
A. 第271条(f)の要素―解決済みの法と未解決の法
第271 条(b)-(c)と第271 条(f)の間にかなりの文言的重複があることを考えると、判例が引き継がれ、271 条(f)に関する法律の多くもそれに応じて解決されたと思われるかもしれない。 そうではない。 一例を挙げれば、裁判所は、第271(f)(1)の「積極的に誘発する」が§271(b)における文言と同じ意味を有するかどうかで意見が分かれている。このような対立が、関連する利害関係者の間で明確性を欠く一因となっているのは間違いない。 本稿の残りの部分では、(可能な限り)法律を解明し、(それが不可能な場合には)問題を鮮明にするために、第271条(f)(1)と(f)(2)の主要な要素を示し、関連する判例を要約し、未解決の問題とそれがなぜ重要なのかを明確にする。
III. 第271条(f)の要素
まず何よりも、第271 条(f)は「部品を...供給」することを対象としている。 WesternGeco, 138 S. Ct. at 2134頁。供給とは、「輸出行為」同上、及び「対象物の物理的な移転」(Cardiac Pacemakers, Inc.v. St. Jude Med., Inc.576 F.3d 1348, 1364 (Fed. Cir. 2009))を指す。したがって、連邦巡回控訴裁は、第271条(f)は、“製品、装置又は機器” に対する主張のような、物に関する特許のみを保護すると判示した。同上。 対照的に、方法又は手続を対象とする特許は、無形の手段又は行為から構成されているため、含まれない。 同様に、第271 条(f)は、「特許化された方法の手段の結果である製品」や「特許化された方法を実行するために使用される製品」には適用されない。なぜなら、これらは特許の「部品」ではなく、むしろ手続や行為である。同上。
第 271 条(f)(1)及び(f)(2)の両方は、「米国内で又は米国から」構成要素を供給することを要件とする。 これは、当該部品が “米国内に物理的に存在し、その後...輸出される ”必要があることを意味する。 Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113, 1117 (Fed. Cir. 2004)。この規定は、「被疑侵害者ではなく、被疑侵害部品の場所に焦点を当てる」ものである。 同上。したがって、米国内の製造業者が、米国外に存在する部品を供給させることは、第271 条(f)の違反にはならない。 同上、1118頁。 また、単に米国から部品を「供給することを申し出る」ことも侵害とはならない。 Rotec Indus., Inc. v. Mitsubishi Corp., 215 F.3d 1246, 1257-58 (Fed. Cir. 2000).
また、第271条(f)は、海外で「組み立てられる」ために供給される「特許発明の構成要素」のみに適用される。 「構成要素」とは、「構成する部分」、「要素」又は「材料」のことであり、実際に海外で組み立てるために「使用可能で、組み立て可能な部品」として供給される必要がある。 Microsoft, 550 U.S. at 449. したがって、最高裁は、第271条(f)を解釈した最初の判例において、ソフトウェア・コードを含むマスターディスクが海外の製造業者に供給され、その製造業者がディスクのコピーを作成し、それを組み合わせて発明品を形成した場合には、侵害を認めなかった。 同上。 マスターディスクは、実際に組み合わされて侵害品になったわけではないので、「特許発明の構成要素」ではなかった。 同様に、「活性化媒体から切り離された」ソフトウェア自体も、「使用可能で、組み立て可能な部品」ではないので、部品ではない。むしろ、「抽象的なソフトウェア・コードは物理的な具現化を伴わないアイデアであり、そのため、第271条(f)の分類である『組み合わせ』に従う『部品』とは一致しない」。 また、マスターディスクから作成されたソフトウェアコピーは海外で製造されたものであるため、「米国から......供給」されたものではない。
B. 第271条(f)(1)の要素
第271条(f)(1)は、「特許発明の全部又は相当部分の構成要素」の供給を対象としている。 最高裁は最近、Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 580 U.S. 140 (2017)においてこの文言を解釈した。 同判決では、裁判所は、「相当部分の構成要素」とは、重要性の質的な尺度ではなく、「(規模が)大きい」「量的な尺度」であるとした。 同146-47頁。すなわち、同文言は供給された「構成要素の数」を指すものである。 同上、148頁。 また、裁判所は、法律解釈上、1つの部品は特許法に基づく「相当部分」ではないとした。同上、 149-52頁.
しかし、同裁判所の狭い解釈の判決は、恐らく、答えと同じくらい多くの疑問を生んだ。 例えば、裁判所は、「相当部分とは構成要素の『全部』にどれだけ近接していなければならないか」については言及を避けた。同上。 すなわち、第271 条(f)(1)に基づく責任が発生するためには、どれだけ多くの部品が供給されなければならないのかという疑問である。 疑問の文言とPromega 判決の推論から、いくつかのヒントが得られる。 まず、裁判所は、「相当部分」とは、特許発明の全構成要素のうち、供給された構成要素の割合によって定義される、相対的な比例の概念であることを示唆している。 したがって、問題は、その比率が100%に「どれだけ近いか」である。 そして、この文言も、少なくとも「近い」ものでなければならない、という部分的な答えを示唆していると言ってよいだろう。 Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners at 25-26, 2016 WL 4728374, Life Techs. Corp. v. Promega Corp., 580 U.S. 140(「第271 条(f)(1) ... は、全部又は全部に近い物の供給に及ぶと適切に解釈される」)参照。
これに関連して、裁判所は、「特許の『構成要素』をどのように特定するか、又はその問題が特許請求の範囲の要素に関係するかどうか、関係するとすればどのように関係するか」についても説明することを避けた。 Life Tech., 580 U.S. at 151 n.2. つまり、「相当部分」は供給された構成要素の数に言及しているが、裁判所は、問題となる構成要素の数をどのように数えるかについて、何の指針も示していない。 裁判所は、構成要素とは「構成部分」または「要素」であると述べているが(Microsoft, 550 U.S. at 449 n.11)、これも多くの疑問を残している。 例えば、構成要素の構成要素、つまり準構成要素は、技術的には発明の製造に使用される部品であるため、数に含まれるのだろうか。もしそうなら、数え方を制限する原則は何か―ネジの1本1本に至るまで数える必要があるのだろうか。これに関連する問いとして、(もし関係するのであれば)この問題は特許請求の範囲とどのように関係するのだろうか。 例えば、問題となる構成要素の数を決定するためには、特許の説明文だけを見るのか、それとも侵害品を作るために実際に使用された部品も関係するのか。 また、被告製品が特許請求の範囲に記載されている部品と異なる種類や量の部品を含んでいる可能性のある、均等論についても検討したい。このような場合、別のルールが適用されるべきなのだろうか? 裁判所は、これらの問題やその他の問題を下級審が解決するよう委ねた。 しかし、残念ながら、Promega 判決以降、これらの問題に取り組んだ裁判所は-地裁でさえも―存在しない。
第 271 条(f)(1)は、被告が米国外で侵害となる組み立てを「積極的に誘発する」ことも要件とする。 前述のとおり、裁判所は、第271 条(b)の文言を明示的に取り込んでいるにもかかわらず、この用語を定義することに苦慮してきた。 例えば、連邦巡回裁判所は、被疑侵害者が、自分自身を侵害の組み立てを行うよう誘発する対象とできると判示した;これは(b)項が第三者に対する誘発のみに適用されることとは対照的である。Promega Corp. v. Life Techs. Corp., 875 F.3d 651, 654 (Fed. Cir. 2017)。
最後に、第271 条(f)(1)の下で要求される故意についても、裁判所の意見は分かれている。 連邦巡回裁判所を含む多くの裁判所は、第271条(b)におけるものと同じ精神状態を要求しているが(以下の事例を参照。Liquid Dynamics Corp. v. Vaughan Co., 449 F.3d 1209, 1222 (Fed. Cir. 2006); Twentieth Century Fox Home Ent. LLC v. Nissim Corp., 2015 WL 3465838, at *2 (S.D. Fla. June 1, 2015) (「第271条(f)の主張は、侵害の具体的な意図を示すことを必要とする」),「国内で組み立てれば侵害が生じることを侵害者が知っていたかどうかに関わらず」組み立てる意図のみを要求している裁判所もある。 WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp., 791 F.3d 1340, 1343-44 (Fed.Cir.2015). これは、第271条(f)の判例法にさらなる不確実性をもたらすが、(b)項と(f)(1)項の故意の要件は同じであり、裁判所は一般的にそのように判示すると考える十分な理由がある。 最も重要なものとしては、この判例が連邦巡回区を拘束するものであり続けることである。Liquid Dynamics, 449 F.3d at 1222。
C. 第271条(f)(2)の要素
第271 条(f)(1)の場合とは異なり、裁判所は、第271 条(f)(2)の意味と範囲については概ね同意しているようである。 とりわけ、この規定は、一般に、第271条(c)と整合的に解釈される。したがって、以下のとおり一般に解されている: (i) (f)(2)項は、複数の構成要素からなる発明のうちの単一の構成要素を供給した場合にも適用される、 580 U.S. at 150参照; (ii) その構成要素は「特別に製造され」たものでなければならず、「侵害しない使用に適した」汎用品であってはならない; (iii) 被告は、第(c)項の場合と同様の故意―特許及び侵害の知識を含む―を有するだけでなく、「米国外において」侵害となる組み立てを行うという特定の意図も有していなければならない; Veeco Instrument Inc. v. SGL Carbon, LLC, 2017 WL 5054711, at *22 (E.D.N.Y. Nov. 2, 2017)参照; 及び (iv) 構成要素が海外で侵害となる組み合わせに実際に組み立てられる必要はなく、「侵害者がそれらを組み立てる意図を持って出荷」していればよい」Waymark Corp. v. Porta Sys. 245 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2001)。 対照的に、裁判所は一般的に、271 条(f)(1)については外国での最終的な組み立てを要件としていると判示する。 Microsoft, 550 U.S. at 453(「米国から供給された構成要素そのものが...海外で組み立てられて、問題となる特許発明を形成した場合、271条(f)の責任を引き起こす」)、Jacobs Vehicle Sys. D. Conn. 2006)(第 271 条(f)(2)は、第 271 条(f)(1)とは異なり、海外での最終組み立てを必要としないと判示した)参照。
第271 条(f)を検討した最新の事件において、最高裁は、原告が 271 条(f)(2)に基づき、侵害によって失った外国での利益を請求できると判示した。WesternGeco, 138 S. Ct. at 2136。「連邦法は米国の領域管轄内にのみ適用される」という一般的な推定にもかかわらず、最高裁は、特許法は「侵害」に対する損害賠償を認めており、第271条(f)(2)に基づく侵害は、被告が米国から問題となる部品を供給した場合に発生すると結論付けた。 請求する逸失利益を立証するためには、最終の組み立て、販売及び使用を含む、追加の外国での活動が必要であったが、その活動は損害賠償の問題に関わるものであり、根本的な損害の発生とは関係ない。したがって、最高裁は、外国での逸失利益は請求可能であると結論づけた。
WesternGeco 判決 は、多くの疑問を提起している。 第一に、最高裁は、「近因のような他の教義が、特定の事例において、どの程度損害賠償を制限又は排除し得るのか」に言及することを明示的に拒否している。 第2に、最高裁は、その理由が第271条(a)~(c)に適用されるとすれば、どの程度かについても述べていない。 この問題については、裁判所の意見が分かれている。 例えば、Brumfield , Tr. for Ascent Tr. v. IB LLC, 586 F. Supp. 3d 827, 840 (N.D. Ill. 2022) (「一部の裁判所はWesternGecoの理論を第271条(a)侵害に拡張したが、第271条(a)の下では海外販売に対する損害が排除されるという「以前の連邦巡回裁判所の判例を覆す」とする連邦判例は未だ存在しない)を参照。 最後に、WesternGeco 判決は、「侵害者による発明の使用」を補償する合理的なロイヤルティにどの程度適用されるのか明らかではない。35 U.S.C. § 284. 合理的なロイヤルティは外国での販売にも適用されるのか、適用されるとすれば、特許のない構成要素の供給者はどの時点で結合した「発明」を「使用」することになるのか。 これらは、第271 条(f)の意味と格闘する裁判所が、決定しなければならない問題のうちほんの一部に過ぎない。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com