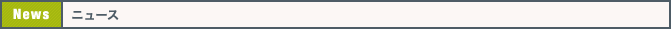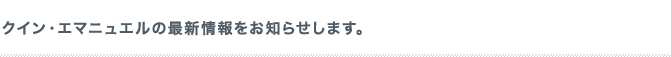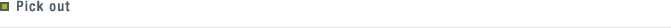お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
ソーシャルメディア企業にとって大きな勝利
米国連邦最高裁判所がテロリズムの責任についてTwitter、Google、Facebookに判決を下し、
230条に基づいてインターネット・プラットフォームに対する責任を再構築するよう求める要求を拒否 (23/06/30)
米国連邦最高裁判所は、Twitter, Inc.対Taamneh事件とGonzalez対Google LLC事件の2つの関連する事件について、注目された判決を発した。 これにより、ソーシャルメディア企業は、各々のプラットフォームに投稿されたテロ関連のコンテンツに関して一般的に責任を負わないとされ、ソーシャルメディア企業に大きな勝利を与えた。しかし同時に、特定のユーザーに対しコンテンツをいわゆる「おすすめ」することに起因する法的責任について、通信品位法230条により技術系プラットフォームが免責されるかどうかという、より重要と思われる問題については、裁判所は判断を保留した。
Taamneh事件及びGonzalez事件は、ISISによるテロ攻撃の犠牲者の遺族が起こした訴訟である。 両事件とも、原告らは、ISISそのものに対してではなく、ソーシャルメディア企業(Twitter、Facebook、Google(YouTubeを所有))に対して損害賠償を求めた。これらの企業は、それぞれのウェブサイトに毎日投稿される何十億ものコンテンツの中に、ISISに関連するコンテンツをも抱えていた。原告らは、このようなコンテンツを抱えることで、各社はテロ攻撃を幇助していたと主張した。 原告らは、「国際テロ行為を行った者に対し故意に実質的支援を行うことによって、これを幇助した者、又はこれと共謀した者」に対して民事責任を課す、2016年のテロ支援者対策法(Justice Against Sponsors of Terrorism Act、以下「JASTA」)を根拠とした。
I. Twitter v. Taamneh事件において、最高裁判所は、ソーシャルメディア企業がISISのテロ攻撃を幇助していないと判断した。
Taamneh事件において、最高裁判所は、原告らの主張はJASTAに基づく企業への責任を課すには不十分であるとし、第9巡回区連邦控訴裁判所の反対判決を覆す判決を全会一致で下した。 同裁判所は、コモンローにおける幇助責任の範囲を、網羅的に検討した上で、JASTAにおける「幇助」は、被告がテロ攻撃に「犯罪に値する程度に参加した」といえるほど、同攻撃に「故意に実質的な援助を与えた」ことを要するとした。 裁判所は、企業がISISに対して 「特別扱いや励ましの言葉 」を与えたり、「ISISのコンテンツに関して(おそらく、その一部をブロックすることを除いて)選択したり、何らかの行動を取ったりした 」という主張はなかったことを指摘し、原告らの主張立証は上記の基準を満たせなかったと結論づけた。
さらに、裁判所は、ソーシャル・メディア・プラットフォームの「単なる作成」は「罪には問えない」と説明した。 一般的な通信プラットフォームの広い文脈の中でこれらのプラットフォームを考えた上で、裁判所は、「ISISのような悪質な行為者は、被告が保有しているようなプラットフォームを違法で、ときに最悪の目的のために利用できるかもしれない」が、一方で「同じことが携帯電話、電子メール、インターネット一般にも言える」と述べ、「インターネットや携帯サービスのプロバイダーが、単にサービスを広く一般大衆に提供するだけで罪を負うとは一般的には考えられない」と述べた。 裁判所は、この点を敷衍し、「このようなプロバイダーは、例えば、携帯電話で仲介された違法な麻薬取引の幇助をするとは通常言えないだろう―たとえ、プロバイダーの会議通話やビデオ通話機能がその取引を容易にしたとしても」と分析した。
同裁判所は、原告らの幇助の理論は技術系プラットフォームがISISコンテンツを削除しなかったとされることに基づいているものの、コモンローは一般的に、単なる不作為に対する責任を課さず、一般的な救助の義務を課すものではない、と付け加えた。 「これに反する判例は、事実上、あらゆる種類のコミュニケーション・プロバイダーに、不正行為者がそのサービスを利用していることを知りながらそれを止めなかったというだけで、あらゆる種類の不正行為に対する責任を負わせることになってしまう」と裁判所は説明した。
II. Gonzalez v. Google事件において、裁判所は、通信品位法230条がいわゆる 「おすすめ」に対して別個の免責を与えるかどうかについて判断しなかった
Gonzalez事件は、Taamneh事件と類似の事実を含むが、広範囲に及ぶ可能性のある別の問題を提起した。現代のインターネットの中心的な法令である通信品位法230条は、ソーシャルメディア企業が特定のユーザーに対してアルゴリズムを使用してコンテンツを「おすすめ」することから生じる責任を免責するかどうかである。
1996年の制定当時、230条は、インタラクティブなウェブサイトが、第三者によってアップロードされたコンテンツに対して、名誉毀損訴訟などの責任を負う可能性があるという懸念に対処するものであった。 このような責任を回避するため、230条は、ウェブサイトを「他の情報コンテンツプロバイダーが提供する情報の発行者または発言者として扱ってはならない」と規定している。 Gonzalez事件において、原告らは、過去の視聴傾向に基づいて個々のユーザーに対しコンテンツを選択し、特定のユーザーにISISのビデオを「おすすめ」したとされるYouTubeの「おすすめ」のアルゴリズムは、230条の免責に包まれないと主張した。 230条の免責を支持する主張として、企業側は、動画の選別とグルーピング(すなわち、アルゴリズムによる「おすすめ」)は、単にソーシャルメディア・プラットフォームで掲載される膨大な量の情報を整理するために必要な要素に過ぎず、230条によって保護される伝統的な出版者の機能であると反論した。
しかし、最高裁は、最終的に230条の問題には触れないことを選択した。最高裁は、その代わりに、Taamneh事件で採用されたJASTAの幇助規定の解釈によれば、Gonzalez事件の原告らは、230条の適用可能性にかかわらず、勝訴しない可能性が高いと判断した。このように、裁判所は、この事件が提示した、より重大であろう問題を事実上回避し、一般的にインターネット・プラットフォームに有利である第9巡回区裁判所による230条の解釈をそのまま残した。 最高裁は、第9巡回区裁判所の判決を取り消し、原告の訴状をTaamneh事件の判決に照らして検討するよう指示して、同裁判所に差し戻した。
しかし、最高裁は、Taamnehにおいて、230条の問題を最終的にどのように解決する可能性があるかについて、いくつかの手がかりを残している。 とりわけ、最高裁は、プラットフォームの「『おすすめ』アルゴリズムは受動的な援助を超え、積極的で実質的な援助に該当する」という原告らの主張に「同意しない」と述べた。それどころか、最高裁は、「アルゴリズムは、コンテンツの性質とは関係なく、あらゆるコンテンツ(ISISのコンテンツを含む)を、そのコンテンツを見る可能性が高いあらゆるユーザーとマッチングさせる」ものであり、「ひとたびプラットフォームと選別ツールのアルゴリズムが稼働してからは、被告の関与は、せいぜい静観していた程度に過ぎない」と説明した。 このように、裁判所は、「おすすめ」アルゴリズムを単なる受動的な組織化ツール、したがってインターネット上で第三者のコンテンツを公開するインフラの単なる一部とみなしているようである。
III. 今回の決定は、ソーシャルメディア企業にとって大きな勝利を意味する。
Taamneh事件とGonzalez事件は、ソーシャルメディア・プラットフォームにとって実質的な勝利となる。 Taamneh事件は、ソーシャルメディアのフォロワーを持つグループによるテロ攻撃に対してソーシャルメディア企業が幇助責任を負う可能性があるという主張を退けることにより、ほぼすべてのテロの凶行から生じる可能性があった多大な責任から企業を保護した。 また、Gonzalez事件で裁判所は230条に関する問題を回避したが、テック企業は控訴審の有利な裁判例を保持し、少なくとも当分の間は230条の免責の範囲を縮小するような悲惨な可能性は避けられた。 以前の個別意見(Taamneh事件の判決を書いたThomas裁判官を含む)は、裁判所が230条をより狭く解釈する傾向にあることを示唆していたため、これは事実上の勝利以上のものである。 しかし、将来、同裁判所が再び230条の問題を取り上げるリスクは残されている。
クイン・エマニュエルは、Gonzalez v. Google LLCの最高裁判決において、複数のインターネット企業を代理して、Googleを支持するアミカスブリーフを提出しました。
※アミカスブリーフは当事者及び参加人以外の第三者から意見や資料を提出することで、日本版は昨年9月、知財高裁で初めて採用されています。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com