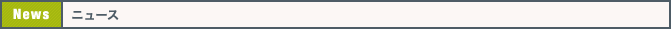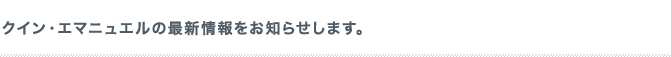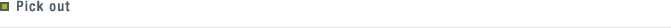お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
変化するDOJの刑事執行方針について企業が知っておくべきこと
(23/09/01)
米国司法省(以下「DOJ」)は最近、企業起訴に関する異例の多数の方針改定を発表し、自発的な自己開示、企業の協力とコンプライアンス、および企業の従業員、個人の起訴に対するDOJのアプローチに影響を与えることとなった。これらの改定は、Lisa Monaco司法副長官の2022年9月の覚書(以下「モナコ・メモ」)に由来し、これをさらに詳しく説明したものである。この覚書は、企業が自主的に不祥事を自己開示することを奨励する政策を実施し、捜査に全面的に協力し、不正行為を抑止する報酬制度を採用し、業務を遂行するための個人用デバイスやサードパーティのメッセージング・アプリケーションの使用を規制する政策を制定するよう、DOJの各部門に指示したものである。
2023年1月、Kenneth A. Polite, Jr.検事総長補(以下「AAG Polite」)は、DOJの刑事局が2017年以来初めて企業執行方針(以下「CEP」)を改定すると発表した。続いて2023年3月、AAG Polite氏は、不正行為を抑止する報酬制度の採用を企業に奨励、特定の電子通信および電子機器の使用を規制するため、刑事局が企業コンプライアンス・プログラムの評価方針(以下「ECCPポリシー」)を改定すると発表した。副司法長官はまた、企業の不祥事に関する米国検事局(以下「USAO」)の自発的自己開示方針(以下「VSDポリシー」)を承認した。さらに、刑事管轄権も有するDOJの民事局消費者保護部(以下「CPB」)は、CPBが執行する様々な消費者保護法に関連する企業の刑事上の不正行為について、新たな自発的自己開示方針(以下「CPB VSD ポリシー」)を発表した。本稿ではこれらの方針変更を要約し、それが企業にとって何を意味するかについて評価する。
コーポレート・エンフォースメント・ポリシー(以下「CEP」)の改訂
刑事局が2023年1月に改訂したCEPは、刑事局が企業刑事案件の監督する方法をより統一し、企業による企業不祥事の自己開示に対してインセンティブを与えることを目的としている。刑事局は以前、企業不祥事を含む案件の執行に関する方針を整備してはいたものの、これらの方針は海外腐敗行為防止法((以下「FCPAポリシー」)案件のみに適用されていた。FCPAポリシー は、企業が自発的に不祥事を自己開示した場合に、その企業が功績を認められるための基準を定めていたが、刑事局はこのポリシーを厳格に適用し、一部の基準しか満たさない企業には、その功績を認める機会を正式には提供していなかった。改正されたCEPは、すべての企業刑事案件に適用されるが、FCPA案件に関する刑事局のより狭義の方針を基礎としており、企業が訴追を回避や刑事罰の軽減を得たりするためのより多くの道を確立するものである。
FCPAポリシー と同様に、CEPは以下の場合、DOJが企業の刑事上の不正行為を訴追しないという前提を設けている:(1)企業が自発的に不正行為を刑事局に自己開示する、(2)企業が刑事局の調査に全面的に協力する、(3)企業が関連する全ての不正行為を適時適切に是正する、そして (4)問題となる不正行為に関連する加重すべき状況がない場合である。さらに、企業は不正行為に起因するすべての遺贈、没収、および/または賠償義務による支払いに同意しなければならない。
CEPは、企業がこれらの各要素をいかにして満たすのかについてその方法に重大な変更は加えていない:
• 自発的な自己開示:
企業は、不正行為に気づいてから合理的な時間内に、また米国連邦量刑ガイドライン(以下「USSG」)に従い、開示や政府による捜査といった差し迫った脅威が生じる前に、刑事局に不正行為を開示しなければならない。企業は、不祥事に関与した、または不祥事に責任を負うとわかっている個人に関する情報を含むがこれに限定されない、不祥事に関するすべての関連する非公開の事実と証拠を開示しなければならない。合意(例えば、不起訴合意)によって、問題となっている不祥事を開示する既存の義務が企業に課せられている場合には、企業は自発的に自己開示したことにはならない。
• 全面的な協力:
企業は、問題となっている不祥事に関連するすべての非特権事実を適時に開示し、あらゆる捜査に積極的に協力し(たとえ要求されていなくても、関連するすべての事実を開示するなど)、不祥事に関連するすべての関連文書や情報を適時かつ自発的に収集、保存、開示しなければならない。また、企業は不祥事に関する企業の内部調査が、対応するDOJの調査と衝突したり干渉したりしないような措置を講じなければならず、関連情報を保有する従業員や役員を、憲法修正第5条の下で許される範囲で、刑事局との面談に応じさせなければならない。これらの要件は、FCPAポリシーの要件を反映したものである。
• 適時かつ適切な是正:
企業は、不祥事の根本原因を特定し、是正し、効果的なコンプライアンスおよび倫理プログラムを実施し、不祥事に責任のある従業員を適切に懲戒処分し、業務記録を保持し、不適切な削除や破棄を禁止しなければならない(業務遂行のための個人的な通信やサードパーティのメッセージング・アプリケーションの使用を規制する管理を実施することを含む)。効果的なコンプライアンスと倫理プログラムを実施するために、どのような基準に従わなければならないかは、企業の性質、資源、規模によって異なる。企業はまた、不祥事の重大性を理解し、責任を受け入れ、不祥事を繰り返さないためのセーフガードを導入したことを示すその他の措置を講じたことを示さなければならない。
• 加重すべき状況:
一般に加重すべき状況が存在する場合、起訴断念の推定は排除される。加重すべき状況には以下が含まれるが、これらに限定されるものではない:(1)不正行為への企業経営陣の関与、(2)企業全体の利益に比して多額の利益を上げる原因となったような不正行為、(3)悪質な不正行為または蔓延した不正行為、そして(4)犯罪の再犯、である。FCPAポリシーでも、同じ加重すべき状況が規定されている。
その前身とは異なり、CEPでは不正行為に関与した企業が刑事罰の軽減を得るための複数の経路が設けられている。FCPAポリシーの下では、企業の自発的な自己開示、全面的な協力、適時適切な是正は、たとえDOJが、加重すべき状況が存在しており刑事処分が正当化されると判断した場合であっても、刑事罰の軽減につながる。このような場合には、FCPAポリシーは検察官に対しUSSGの罰金額の下限から50%減額することに同意すること、もしくは量刑裁判所に対してそうするよう示唆するよう指示した。さらに、FCPAポリシーは、独立したモニターを任命する義務から協力企業を免除するよう検察官に指示した。このシナリオ以外では、FCPAポリシーは、「各事例の状況に基づき、(企業の)協力の範囲、量、質、タイミングを評価する」ため検察官の裁量を広く認めているが、代替的な救済措置に関する具体的な基準は規定していない。
CEPは、より多くの企業が自発的に不祥事を自己開示し、DOJの調査に協力するよう促すため、この執行パラダイムに4つの重要な変更を加えた。第一 に、CEPは刑事罰の推奨減額率を50%から50~75%に引き上げた。第二 に、CEPは検察官に対し、加重すべき状況が特に多いか悪質でない限り、協力的な企業に対し有罪答弁を提出するよう要求しないよう指示した。第三 に、加重状況の存在により起訴断念の推定が排除される場合であっても、それでもなお検察官が起訴を断念することができるのは、以下の場合であるとしている:
• 不正行為を認識した後、直ちに自発的に自己開示した場合、
• 不正行為および開示が発生した時点で、効果的なコンプライアンス・プログラムおよび内部会計管理システムを維持していた場合、それから
• DOJの調査に協力し、不正行為を是正するための特別な措置を講じていた場合
AAG Polite氏によると、検察官は「即時性、一貫性、程度、影響」を考慮し、協力と是正の措置が並外れたものであるかどうかを判断する。AAG Polite氏によると、刑事局は個人または法人が、(1)「直ちに協力を開始し、一貫して真実を語る」、(2)「電子デバイスを迅速に入手して画像化する、会話を録音するなど、(刑事局が)他の方法では入手できない証拠を入手できるようにする」、それから (3)「公判で証言する、追加有罪判決につながる情報を提供するなどの成果を生む」形で協力する、といった場合評価している。
第四 に、CEPの下では、自発的な自己開示がないことは、刑事罰の減免を必ずしも妨げるものではなくなった。当初は自発的に不祥事を自己開示しなかったが、後に全面的に協力し、適時適切に改善した企業は、USSGの罰金額の下限から最大50%の減額を受ける権利を有するようになったのである。
企業コンプライアンス・プログラム(「ECCP」)ポリシーの改訂の評価
長年にわたり刑事局のECCPポリシーは、検察官が不祥事を起訴するかどうか、またどのようにそれを行うのかを決定する際に、彼らが企業のコンプライアンス・プログラムの適切性を評価するのに役立つよう運用されてきた。ECCPポリシーの下、検察官は、 (1)企業のコンプライアンス・プログラムが「よく設計」されているか、(2)そのプログラムが 「真摯かつ誠実に」実施されているか、それから (3)そのプログラムが 「実際に機能しているか」を確認しなければならないようになっている。
2023年3月、AAG Polite氏は、モナコ・メモの指令を実施するためのECCPポリシーへの変更を発表した。これらの変更は企業に対し、(1)従業員が業務を遂行するために個人用デバイスおよび/またはサードパーティのメッセージング・アプリケーションをどのように使用するかを規制するポリシーを制定し、実施すること、および (2)不正行為を抑止する報酬制度を採用することを奨励しようとするものである。ECCPポリシーは、企業が問題となる不正行為に関与する前に、不正行為を抑止しコンプライアンスを促進する社内プロトコルやシステムを採用していた場合、検察官が刑事罰を軽減することを奨励している。
個人用デバイスの使用を管理するポリシー。改訂されたECCPポリシーの下、企業のコンプライアンス・プログラムの有効性を評価する検察官は、以下を考慮しなければならなくなった:
• 企業が従業員に業務遂行のために使用することを許可している電子通信の方法(自動消滅または自己消滅するメッセージを使用するサードパーティのメッセージングアプリケーションを含む)
• 企業が、従業員に対し、「Bring-your-own-device」プログラムなどを通じて、業務遂行のために個人所有の電子機器を使用することを許可しているかどうか、またどのように許可しているか
• 会社が保存と削除のプロトコルを実施しているかどうか、またどのように実施するのか、そして
• 企業がこれらの方針と手順を従業員にどのように伝えているか
重要なのは、企業がDOJの捜査の一環としてサードパーティのメッセージング・アプリケーションからの通信を提示しなかった場合、改訂されたECCPポリシーは、企業がそのような通信にアクセスできるかどうかを考慮に入れるよう検察官に指示することである。
報酬制度。改定されたECCPポリシーはまた、不正行為を起訴するか、またどのように起訴するかを決定する際に、企業の報酬制度を考慮するよう検察官に指示している。具体的には、検察官は、従業員が不祥事を起こした場合、企業の報酬制度が報酬の繰り延べ、エスクロー、または保有し支払うことを控えるように設計されているかを評価しなければならない。
AAG Polite氏は、ECCPポリシーの変更を発表した後、刑事局が3年間の「報酬インセンティブとクローバックに関するパイロット・プログラム」(以下「パイロット・プログラム」)を開始したことも明らかにした。AAG Polite氏によると、このパイロット・プログラムは、「クローバック・ポリシーの使用を含む[通じて]報酬制度を通じて、より良いコンプライアンスを奨励する解決策を策定した企業に報いる」ことを意図しているものである。パイロット・プログラムでは、刑事局と刑事上の解決を結んだ企業は、報酬や賞与制度にコンプライアンス関連の基準を導入し、その進捗状況を定期的に刑事局に報告しなければならないことになっている。 コンプライアンス関連基準には、以下が含まれるが、これらに限定されるものではない: (1)コンプライアンス業績要件を満たさない従業員に対する賞与の禁止、(2)適用される法律や方針に違反した従業員に対する懲戒処分、そして (3)コンプライアンス・プロセスに全面的にコミットした従業員に対するインセンティブ。
パイロット・プログラムはまた、以下のような従業員から報酬を回収する「クローバック」ポリシーを持つ企業に対する刑事罰の軽減を検討するよう、検察局に指示している。これらの従業員は:(1)不正行為に関与した従業員または業務領域に対する監督権限を保持していた者、また (2)不正行為を知っていた、または故意に見て見ぬふりをしていた者たちである。
企業が捜査に全面的に協力し、不祥事を適時かつ適切に改善し、ECCPポリシーに従ってコンプライアンス関連の基準を実施したことを立証した場合、パイロット・プログラムでは、刑事上の解決期間中に回収された報酬の100%を、刑事局が該当する罰金として減額することができる。最終的には、そのような報酬を回収するための企業の誠意ある取り組みが失敗した場合には、検察官は企業が回収を試みた報酬額の最大25%まで罰金を減額することができる裁量権を有している。
USAOの自発的自己開示方針(「USAO VSDポリシー」)
2023年2月下旬、司法副長官事務室はすべての連邦検事局に適用されるUSAO VSDポリシーを承認した。ニューヨーク州東部地区連邦検事Breon Peace氏とニューヨーク州南部地区連邦検事Damian Williams氏は、司法長官諮問委員会のホワイトカラー詐欺小委員会と共同でUSAO VSD方針を策定した後にそれを共同で発表した。Peace連邦検事は、USAO VSDポリシーは「企業が自発的な自己開示を行ったかどうかを連邦検事局がどのように判断するかの基準を提供しており、(そうすることでの)企業にとっての特定で具体的な利益を透明化しており. . . [そしてその]結果、企業がどこの国で事業を営んでいようとも、米国司法当局に犯罪行為を自発的に自己開示することで、同じ待遇と利益を受けることができる。」ものであると述べた。
USAO VSDポリシーでは、加重すべき要因がない限り、自主的に不正行為を自己開示し、全面的に協力し、適時に適切な是正を行い、問題の不正行為に起因するすべての遺贈、没収、賠償金の支払いに同意した企業に対しては、有罪答弁を求めないと明確に定められている。さらにUSAOは、刑事処分の時点で企業が「効果的な」コンプライアンス・プログラムを実施しテストしている限り、独立したモニターの選任を要求しない。最後に、USAOは適用される刑事罰をUSSGの罰金範囲の下限から最大50%減額するかをケースバイケースで決定する。
USAO VSDポリシーは、CEPで定められた定義をほぼ採用している。しかし、USAO VSDポリシーの下では、有罪答弁を正当化する可能性のある加重すべき要因には以下のものが含まれている:(1) 国家安全保障、公衆衛生、環境に対する重大な脅威となる不正行為、(2) 深く蔓延した不正行為、もしくは (3) 企業の現経営陣が関与する不正行為である。 さらにUSAO VSDポリシーでは、検察官が独立したモニターの選任を要求するかどうかを決定する際には、モナコ・メモ、ECCPポリシー、およびDOJの各部門が公布したその他のガイダンスに依拠すべきとしている。「モニターの必要性についての決定は、ケースバイケースで、USAOの単独の裁量で行われることとする。」
最終的に、加重すべき要因が存在し、USAOが有罪答弁を求めても、企業が自発的に自己開示し、全面的に協力し、適時適切に改善した場合、USAOは (1)USSGの罰金額の下限から50~75%減額することに同意する、もしくは量刑裁判所に対してそうするよう示唆し、そして (2)企業が効果的なコンプライアンス・プログラムを実施しテストしている限り、モニターを任命する義務を免除する。
CPBの自発的自己開示ポリシー(「CPB VSDポリシー」)
2023年3月初旬にDOJの民事局消費者保護部門は、CPBが執行する消費者の健康、安全、経済安全保障、データプライバシー、および詐欺に関する法律の刑事規定に関連する不正行為を企業が自主的に自己開示する方法を規定する、新しいCPB VSDポリシーを発表した。USAOのVSDポリシーと同様に、CPBはCEPを考案するにあたり、刑事局が定めた定義を採用している。
CPB VSDポリシーは、加重要因が存在しない限り、CPBは、自発的に不正行為を自己開示し、全面的に協力し、適時適切に改善する企業に対して有罪答弁を求めないと規定している。CEPが想定している措置以外にも、「特定可能な被害者への賠償や、将来の違法行為に関与するリスクを軽減するための(企業の)コンプライアンス・プログラムの改善」も是正の中に含まれる。さらにCPBは、企業が刑事上の解決時に「効果的な」コンプライアンス・プログラムを実施し、テストしている限り、独立したモニターの選任を要求しない。
CPB検察官が企業に対して「より厳格な」刑事処分を求める可能性のある加重すべき要因には、以下のものが含まれるが、これらに限定されるわけではない:(1)意図的または故意に消費者を死亡または重篤な身体傷害の重大な危険にさらすような不正行為、 (2)意図的または故意に高齢者、移民、退役軍人、軍人などの弱い立場の被害者を標的にした不正行為、(3)深く蔓延した不正行為、もしくは (4)上層部が故意に関与している不正行為。USAOは、協力的な企業が受けることのできる刑事罰の具体的な軽減について詳述しているものの、CPBのVSDポリシーでは、企業が自発的に不祥事を自己開示した場合、企業には「その功績を認められる」権利があるとだけ言及がされている。
要点
DOJとその各部門は、このような新しい方針とインセンティブ構造の明確化を通じて、検察官が企業の犯罪行為をどのように捜査・起訴すべきかについて、より統一性を持たせる一方、企業には不祥事の自己開示と是正についてより柔軟性を提供しようとしている。企業は積極的に新しい方針を導入し、既存の方針を監査して、これらの改正を考慮すべきである。
しかし、当然のことながら、モナコ・メモもその後の方針改訂も、自発的な自己開示に関する明瞭な線引きルールを確立するものではない。企業の不祥事が、同じ結果をもたらすほど類似している例はほとんどないことを考えると、企業が不祥事に関与したという疑惑をどのように扱うか、またその企業が訴追を回避することや刑事罰の軽減を得るために必要となる要件を満たしているかどうかを判断するDOJの意思決定プロセスにおいて、検察官の裁量は依然として原動力となるであろう。しかし、企業が最近のDOJの方針発表を遵守していることを明確に示すことができれば、DOJとその部門が発表したインセンティブ構造より恩恵を受ける可能性を最大限に高めることができるのである。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com