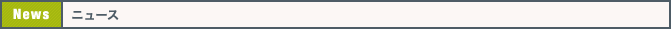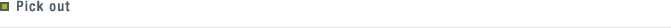お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
「最高裁、著作権法の3年の時効期間外に発生した侵害行為に対する損害賠償請求の可否を検討」
(24/04/26)
最高裁において、著作権訴訟における損害賠償の範囲に重大な影響を及ぼすと思われる訴訟の弁論が行われた。 Nealy v. Warner Chappel Music, Inc.事件では、裁判所は、ディスカバリー・ルールに基づき、著作権法の3年の時効期間外に発生した侵害行為について、著作権を有する原告が損害賠償を請求できるかどうかの判断を求めている。 ディスカバリー・ルールは一般的に、原告がその請求原因事実を発見した時点、または合理的に発見すべきであった時点から時効期間を計算するのに対し、傷害ルールは著作権事件における時効期間を侵害行為から計算する。この事件において、 被告は、第11巡回区判決の破棄を求めている。第11巡回区判決は、ディスカバリー・ルールに基づき原告が適時に訴訟を開始した場合、著作権法の3年の時効は原告が訴訟を提起する3年以上前、かつ原告の請求の発見前に発生した行為に対する損害賠償を得ることを妨げないと判事したものである。
この問題については、主に2014年に最高裁が下したPetrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. 判決(572 U.S. 663頁)に対する解釈の違いから、各裁判所で意見が分かれている。同判決で、被告は、著作権法が定める訴訟開始3年以内の行為に対する損害賠償を求める適時の請求を禁止するために、懈怠責任の原則を援用することはできないとした。(すなわち、訴訟を提起するにあたり不合理で不利な遅延があった場合、損害賠償を得られないとする考え方を援用することはできないとした) 667頁。
同裁判所は、分離的発生ルールの下では、侵害行為の一つ一つが「新たな制限期間を開始する」ものであり、原告は制限期間内の侵害行為に対してのみ損害賠償を求めたと指摘した。668、671頁。 従って、被告は、原告が制限期間外の侵害行為について訴訟を提起しなかったことにより、制限期間内の侵害行為に関する損害賠償請求が禁止されると主張するために懈怠責任を使用することはできない。同裁判所は判決に至るにあたり、同法の時効は「それ自体が遅延を考慮したもの」であると説明した。なぜなら、原告は「提訴の時点から遡って3年間しか救済を受けることができず」、「それ以前の期間の侵害については回復を受けることができない」からである。 677頁参照。 同裁判所は、著作権訴訟においてディスカバリー・ルールが適用されるかどうかという問題については言及していない。 670 n.4参照。
第2巡回区は、請求の発生時期を決定するためにディスカバリー・ルールが適用される場合であっても、著作権法はそれにもかかわらず、損害回復を「提訴前の3年間に発生した損害」に限定することを意味するとPetrella判決を解釈した。 Sohm v. Scholastic Inc., 959 F.3d 39, 52 (2d Cir. 2020)を参照。 第9巡回区と第11巡回区はこの解釈に同意していない。 両法廷は、同法の3年の時効は、原告がその主張を発見する前に発生した侵害行為や、合理的に発見すべきであった侵害行為については、それが訴訟の3年以上前に発生したものであっても、損害賠償の回復を妨げるものではないとしている。 Starz Entm't, LLC v. MGM Domestic Television Dist., LLC, 39 F.4th 1236 (9th Cir. 2022); Nealy v. Warner Chappel Music, Inc., 60 F.4th 1325 (11th Cir. 2023)を参照。 第9巡回区は、第2巡回区の解釈は "ディスカバリー・ルールを根底から覆す "と述べている。 Starz Entm't, 39 F.4th at 1244. 第11巡回控訴裁は、Petrella判決の反対解釈は、「提示された問題を無視し、傷害ルールに基づく請求の発生とディスカバリー・ルールに基づく損害賠償の可否に関する裁判所の議論を混同しており、裁判所がディスカバリー・ルールを明示的に維持していることと矛盾する」と説明した。 Nealy, 60 F.4th at 1334.
Petrella判決の解釈の議論に加え、Warner事件の両当事者は、著作権法の時効が回復可能な損害賠償の範囲を規定しているかどうかについても意見が分かれている。 原告は、著作権法第507条(b)に規定される民事請求の時効期間は、訴訟を提起することができる時期のみを決定するものであり、回復可能な損害賠償の範囲を決定するものではないと主張する。 同条は、民事訴訟は請求の発生から3年以内に開始されない限り提起できないと定めている。 第504条は、著作権者が「被った実際の損害」と侵害に起因する「あらゆる利益」を回復できると規定している。 原告はまた、著作権法の他の条文も指摘し、議会が特定の種類の著作権侵害に対する損害賠償の時間的範囲を制限しようとする場合、議会は明確に示したはずであると主張している。
被告は特に、著作権事件におけるディスカバリー・ルールの適用範囲は限定されるべきであり、伝統的に適用されてきた、詐欺、潜在性疾患、医療過誤の場合とは異なると主張している。 原告は、このような議論は、裁判所がディスカバリー・ルールの適用を前提に修正した主張の域を出ると主張している。弁論中、何人かの裁判官は、提示された問題に照らして、裁判所がこの訴訟においてディスカバリー・ルールの適用範囲を決定することが適切かどうか疑問を呈した。 別事件であるMartinelli v. Hearst Newspapers LLC事件では、著作権事件においてディスカバリー・ルールが全く適用されないかどうかという問題に関して、現在最高裁判所に審議が係属中である。
Warner事件における裁判所の判断は、ディスカバリー・ルールが適用される著作権訴訟において原告が回復できる損害賠償の範囲に重要な影響を与える可能性がある。 現在の判例では、第2巡回区で提訴した原告は、提訴の3年以上前に発生した侵害行為に対する損害賠償を得ることができないが、他のある巡回区では、ディスカバリー・ルールが適用され、提訴が適時に行われた場合には、そのような損害賠償の回復が認められている。 したがって、どちらか一方に統一されたルールが適用されれば、ディスカバリー・ルールが適用された場合に回復可能な損害賠償の範囲が拡大されるか狭められることになる。 Nealy事件では、原告は2018年に訴訟を起こしたが、2008年までさかのぼる侵害の疑いに対する損害賠償を請求しており、この問題に対する裁判所の判断が今後の著作権訴訟においてどのような違いをもたらすかを示している。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com